BS-TBS番組情報 №303 [雑木林の四季]
BS-TBS 2024年4月後半のおすすめ番組
BS-TBSマーケティングPR部
BS-TBSマーケティングPR部
関口宏のこの先どうなる!?

4月21日(日)ひる12:00~12:54
☆日曜のお昼は関口宏と未来について考える!世界が抱える〝今〟の問題と日本の〝未来〟を紐解いていく。
<司会> 関口宏
<オブザーバー> 川口盛之助
英国の産業革命から約300年、インターネットの本格登場から約30年、「ChatGPT」の公開からわずか1年強・・・かつてない技術革新のスピードに戸惑い、その功罪に様々な心配を抱くのは、令和世代も昭和世代も同じであろう。この番組では「AI」「医療」「環境問題」「食の安全」など気になる話題すべてをテーマに、世界が抱える〝今〟の問題と、私たちの生活および日本の〝未来〟を紐解いていく。
司会はテレビ人生60年の関口宏。オブザーバーは未来予測研究家の川口盛之助(かわぐちもりのすけ)が務め、ゲストには令和の日本を担う若き専門家たちを迎える。
昭和生まれの関口宏が、各界の専門家の頭脳を拠り所に視聴者の漠然とした不安を解きほぐし 、明るい未来へ導くヒントを提示する〝未来予測番組〟。初回放送は4月20日、「生成 AI」をテーマにお届けする。
ラーメンを食べる。


4月23日(火)よる11時~11時30分
☆仕込みから閉店まで…ラーメン店に密着。最後はラーメンを愛する芸能人が珠玉の一杯を食す!
#7「純手打ち 麺と未来(下北沢)」
下北沢一番街商店街に2018年にオープンした「純手打ち 麺と未来」。看板メニューの「塩ラーメン」は、鶏の手羽肉、アサリ、昆布、カタクチイワシ、かつお節などの素材を凝縮させた出汁に、ミネラル豊富な塩だれをベースにしている。博多うどんにインスパイアされた極太ぶよぶよ麺や、プリプリの海老が入った雲吞も特徴的。
今回ラーメンを実食するのは、毎週火曜よる9時にBS-TBSで放送中のドラマ「御社の乱れ正します!」で主演を務める俳優・山崎紘菜。
こちら歴史ミステリー旅行社 幕末の京都 謎解きツアー
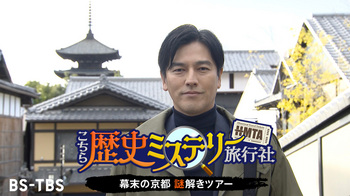
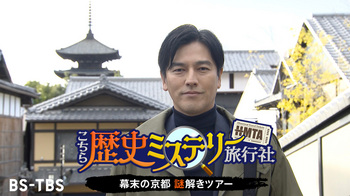
4月27日(土)よる7時~8時54分
☆旅情感にあふれる新たな歴史謎解き旅番組第二弾!今回は幕末の京都!
歴史の謎解きツアーを企画する旅行会社HMTA(Historical Mystery Travel Agency)の企画部社員:要潤が、今回は「幕末の京都ツアー」を企画する。歴史アドバイザーの河合敦さんと共に幕末の京都の謎を解き明かしながら、旅情ある2泊3日のツアープランを作り上げるという歴史紀行番組。
京都で解き明かす、歴史ミステリーは3つ。混乱する京都の治安を守るべく結成された「新選組」は何を目指していたのか?15代将軍・徳川慶喜は、将軍になってわずか10か月でなぜ大政奉還したのか?そして、坂本龍馬はなぜ、誰に暗殺されたのか?
魅力あふれる京都の観光地をめぐり、激動の幕末の舞台を訪ね、歴史の謎にまつわる美味しいものを食べ、絶景の宿に宿泊します。果たして、要潤はどんな旅のプランを完成させるのでしょうか?
海の見る夢 №75 [雑木林の四季]
海の見る夢
-パーフェクトデイズ―
澁澤京子
-パーフェクトデイズ―
澁澤京子
・・元来、僕は美術的なことが好きであるから。実用とともに建築を美術的にしてみようというのがもう一つの理由であった。・・
『落第』夏目漱石~『漱石のデザイン論』川床優からの又引用
『落第』夏目漱石~『漱石のデザイン論』川床優からの又引用
渋谷、六本木、下北沢という昔から親しんだ街は再開発されて変貌が激しく、もうあまり歩きたい街ではなくなってしまった。昔から残っていた商店街とか路地や居酒屋、そうした生活感のある空間がなくなればなくなるほど、街はどんどん無機質なつまらないものになり、街の情緒がなくなる。今、渋谷でにぎわっているのはかつての宮下公園下の飲み屋街であり、店は新しく変わったが路地はそのままの道玄坂百軒店ではないか。これ見よがしの都庁のイルミネーションとか街路樹を伐採するとか、東京を非人間的な都市にするつもりなのだろうか。煌々とライトアップされた桜は明るすぎて、夜桜だったら風に吹かれて揺れる提灯の薄暗い灯りで見たほうが、風情があって美しい。(桜の花というのは闇の中にあると、うすぼんやりと白く浮かんで幻想的なのである)
コルビュジェ式のモダニズム都市再開発に反対し、ニューヨークを救ったのがジェイン・ジェイコブズ。(コルビュジェの構想したパリ再開発も、フランス人の反対にあって実現しなかった)ブルックリンで生まれ育ったジェイコブズは、都会は混とんの中に秩序があることをよく知っており、ハーレムを壊す再開発や高速道路建設計画に反対運動を起こして勝利した。再開発側の人間は政府と結託し、古く汚くなったものを取り除き、過去を清算して新しく作り直せば誰でも便利で快適に暮らせると考えていたが、ジェイコブズはそれを否定した。彼女は人間というものがどういうものなのかをよくわかっていたのである。コルビュジェ式のモダニズム都市計画は車が移動手段であり、街に死角をつくり人のコミュニティを壊すとし、あくまで歩く人の目線で街を考え、自然発生した路地を大切にした。ハーレムは長い年月を通し住民によって自然にできた、生きた道や空間なのであり、実際、シカゴでは都市再開発で計画的に作られた公営住宅はその後スラム化して犯罪の温床となる。今の中国の高層建築の廃墟化もそうした都市再開発によるものだという。今はまた、住む人を中心にして考えたジェイコブズの都市計画が見直されてもいいんじゃないだろうか。
吉祥寺を気に入っているのは、家に帰るときにバスの窓から井の頭公園の緑が見えること。そして迷路のような闇市とか老舗のジャズ・バーとジャズ喫茶がいまだに昔のまま健在なことと、古本屋も多いことだろう。この間、インドに帰る友人のお別れ会の二次会で入ったジャズ喫茶(モア)は、平日の昼間というのに、若者が多くて混んでいたので驚いた。「ブルー・ジャイアント」というジャズ漫画が流行していて、その影響で若いジャズファンが増えたという。(やたら熱いジャズ漫画でした)それにしても、まさかジャズ喫茶が再び活気を見せるとは想像しなかった。私が通っていた頃のジャズ喫茶は、かなりマニアックな常連客のたまり場で敷居が高く、すでに時代から取り残されていたが、今、ジャズはもっとオープンに聴かれているのだろう。ジャズの持つ混沌としたエネルギーに、若い人が惹かれるのはとてもわかる。
最近の「ブルータス」のジャズ特集を読むと、昔のジャズ喫茶のように、友人とのたまり場を兼ね備えた新しいジャズ喫茶、ジャズ・バーも、六本木や高田馬場などに次々とできている様子。日本のジャズ喫茶が逆輸出され、北欧あたりにもぼつぼつとできているらしい。洗足に某大学ジャズ研OBのたまり場(You would be)があり、友人に連れられてそこには何度か足を運んだ。(月に一回、セッションがあります。演奏レベルが高く、オーナーご夫婦がとても優しく居心地がいい)
重いドアを開けるといきなり大音響のジャズ(大抵チャーリー・パーカー)がドアの隙間から漏れてきたかつての百軒店の「Swing」。夕方になると居酒屋(田吾作や焼き鳥屋)からは演歌が流れ、センター街のパチンコ店からは、ピンクレディやキャンディーズなどの歌謡曲が流れていた。昔、渋谷の街を歩くと種々雑多な音楽が流れていて、それが渋谷の街の情緒であり風情にもなっていた。
いまだに古い建物が残っていることと生活の匂いがあることは街の情緒にとっては不可欠で、新しい建物や無駄のない設計に情緒はない。おそらく情緒というものは、全体から生まれるものであり、決して計算から生まれるものではないのだろう。自然が多様性に満ちているように、世界は複雑な無数の絡まりによってできているので、無駄を省くと同時に、人は重要なものも喪失してしまうのではないだろうか?
設計家になりたかった父の影響か、私は不動産広告の間取りを見てあれこれ空想するのが好きだ。間取り。こんなに人の想像力を掻き立てるものってあるだろうか?漱石の小説が好きなのも、漱石の住んでいる家の雰囲気が好きだからと言う事に、ある時気が付いた。漱石の小説には、書斎とか縁側とか厠とか障子とか、どんな間取りの家に住んでいるのかこちらの想像を掻き立てる言葉が頻繁に出てくる。出窓のついた書斎、陽当たりのいい縁側、台所と厠、引き戸になっている暗い玄関、玄関の横のやつで、玄関の上の丸い電灯、祖父の家に似たそうした家を想像してしまう。漱石の文章全体からにじみ出てくるゆとりというのは、きっと漱石の家に似ているのに違いない。漱石の「草枕」を愛読していたグールドの晩年のゴールドベルク変奏曲のゆったりしたテンポは、漱石の文章のテンポに似ていると思うのは私だけだろうか?お金のかかった豪邸が必ずしもゆったりしているわけでもなく、古い木造の小さな家でもゆったりとした品のいい感じの家があるから実に不思議。贅沢なゆとりというのは決してお金から生まれるものじゃないということだろう。
家を探すときは、窓から樹木が見えることを条件にして探しているが、なかなかそうした条件のマンションも家も少ない。私が今住んでいる団地は、偶然にも窓から椋の木とモクレンが見えてうれしいが、去年、オカメインコを探しているうちに近所に、もっといい感じの団地があることを発見した、中庭には樹木が生い茂り住民の憩いの場所になっていて、古いけど温かみのある感じのいい団地。樹木というのはとても重要で、国立という街がいい雰囲気なのも駅前から続く街路樹の木陰と一橋大学の庭の林の存在は大きい。樹木は人の気持ちを落ち着かせる力を持っている。子供のころの東京の住宅街にはまだ大きなお屋敷がところどころに残っていた。お屋敷の庭の樹木がこんもりと生い茂っているせいで、道を歩けばところどころに木陰があったが、それらはマンションに代わって樹木は伐採され、木陰のある住宅街は都内では本当に希少な存在になってしまった。(そして夏はますます高温に)
この間、設計家のFさんにいろいろとお話を伺った。奥多摩に故ラ・サール神父が建てた瞑想の家「神瞑窟」がある。湿気でところどころ朽ちていた「神瞑窟」が、村野藤吾の設計であることを発見したのも、坐禅会にたまたま参加したFさんだった。「神瞑窟」には広い禅堂やお御堂、図書室があり、キリスト教と禅関係の書物がたくさんあり、昔、神父さんが住んでいた部屋には十字架とベッドだけが残され、天井は朽ちて床には無数の虫の死骸が散乱していた。回廊が中心となった不思議な建物と思っていたが、Fさんが発見しなかったら誰にも気が付かれないまま放置されただろう。(その後、Fさんが登録し、建物を修復)亡くなった父が村野藤吾のファンで、箱根プリンスができた時に村野藤吾の設計と言う事で、家族で泊まりに行ったことがあった。
最近のマンションを見ると、部屋がやけに小さくて間取りもチマチマと感じるという話をしたら、最近のマンションの畳サイズは昔より小さく作られているのだとか。昔のアパート、たとえば同潤会アパートなどは小さくても部屋はゆったりと作られていたのだそうだ。原宿の同潤会は有名だが、渋谷桜ケ丘や代官山にも同潤会アパートがあったことを思い出す。桜ヶ丘の同潤会アパートの中庭の真中には古い井戸があった。昔のアパートが狭くてもなんとなく雰囲気があるのは、人の体温を吸収した年月の積み重ねにより、自然に近くなるせいかもしれない。建築を「凍った音楽」と言ったのは誰だか忘れたけど、家も音楽と同じで、結局「情緒」というものがとても重要なのかもしれない。建築も音楽も数学的なものを基礎としながら、情緒を生み出す。演奏家によって同じ曲でも全然違ってくるように、家も、住む人の心が染みつくのだろうか?陽当たりがいいのになんとなく冷たい感じの家もあるし、逆に日当たりが悪くて狭いのになぜか温かい感じの家もある。コンパクトな「風と共に去りぬ」風の家もあれば、斬新なデザインの家もあるし、昔ながらの生垣に囲まれた家もある・・家は視覚化された物語のようで外側から見ているだけでも楽しい。
「パーフェクトデイズという映画をご覧になりましたか?主人公が住んでいるアパートが、都内ではもうほとんど残っていないような昔のアパートで、それが実にいいんですよ。」とFさんに勧められて友人と映画を観に行った。主人公(役所広司)は浅草近辺の古い木造アパートに住んでいる。玄関を開けると急な階段がある二階建てアパートで一階は台所、二階は畳敷きが二間あり一間を寝室にしていて、もう一間には小さな苗木のコレクションが並べてある。毎朝、苗木に霧吹きで水を吹きかけてから公園のトイレ清掃の仕事に出かけ、仕事から帰ると銭湯で汗を流す、家に帰ると、二階の畳敷きの部屋には裸電球がぶらさがっていて、文庫本がきちんと並べられた本棚。毎晩、スタンドの灯りで文庫本を読んでから眠りにつく・・早朝、仕事の車に乗ると缶コーヒーを飲みながらその日のカセットを選び、音楽を聴きながら運転する。ほとんどが60~70年代の音楽で、ルー・リードの「パーフェクトデイズ」が流れる。時々、古本屋の100円コーナーで文庫本を買う、「読書と音楽」の静かな日々。主人公の平山さんはスマホもPCも持たない、もちろんテレビはないし、まるで沈黙の行を守っているかのように寡黙な人なのである。スマホや世間話などで逃避をしないですむのは、内面が豊かで充足しているからであり、「孤独」という贅沢な時間を持てる人であり、今の世の中、こういう豊かな生き方のできる人はほとんど稀で理想的な生き方だろう。小さなカメラで木漏れ日の写真を撮るのが趣味で、夕方には浅草駅構内のカウンター飲み屋に寄る毎日。
そういえば、昔は車で音楽聴くときはカセットテープだったなあと、カセットから流れる音楽といい、私の世代(~上の世代まで)にとっての学生時代の楽しみは「音楽・読書」だったと懐かしい。渋谷のいくつかの大型書店も消え、道玄坂途中の古本屋も、今はなき東急プラザ裏の古本屋もなくなってしまった。本というものは今では無駄なものなのかもしれないが、人が生活からそうした無駄をどんどん排除していくのと同時に情緒も消滅し、つまらない街になってしまったのではないか?『パーフェクトデイズ』の主人公の平山さんは優秀なトイレ清掃員だが、何かをきっかけに今までの生活を捨てた人間だろうということが映画を見ているうちにだんだんわかってくる。お金とか肩書とか名誉、そうした世俗の虚栄から脱出した男の話なのだ。
若い一時期漱石は、協調性がない自分にもできる仕事として、設計家を目指していたというのを『漱石のデザイン論』川床優著 で初めて知ったが、優れた美意識を持った漱石が、建築家を志したというのはとてもわかる。明治時代の漱石全集の柿色の装丁は漱石自身のデザインだが、彼が建築家だったらいったいどんな家を建てただろう?漱石の家はすべて借家だったが、それでも自分の家を建てたいという夢は持っていたという。政治家をはじめとして見せかけがあふれ、漱石のいう「自己本位」(周囲に流されずに自分の意見と主体性を持てる人)で生きる人間がまずます希少になっている今、平山さんは迷わずに「自己本位」の生き方を選んだ人なのである。(妹の訪問で、彼が以前は裕福な生活を送っていた人間だったことがなんとなくわかる)
離婚した森茉莉が浅草あたりの下町に一人で住んでいた時、下町の人間の、決して他人をあれこれ詮索しないが他人を気に掛ける優しさ、下町の人々の人間関係の距離の取り方がとても居心地よくて、パリにいた時のように自由気ままに過ごすことができた、と書いている。昔の東京の下町の人間には「粋」という美意識が残っていたのだと思う。(今もそうした下町の美風が残っているかはわからないが)
幸田露伴は娘に「たとえお金がない時でも、ただ近所を散歩して自然を楽しめるような人が本当の知性ある人間なのだ」と言うような事を娘の文に教えるが、平山さんや漱石はまさに「知性」の人なのであり、そうした「知性」は美意識でもあり、それは孤独の時間によって培われるものだろう。そしてまた、美意識というのは限りなく自然に接近するものじゃないかと思うのである。
住宅団地 記憶と再生 №33 [雑木林の四季]
l9. ベルリン・マルツアーン地区の団地 Ber1in-Marzahn
国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治
国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治
ヘラースドルフ地区の大団地を最初めぐったのは9年前である。その間に、団地の活性化、改造事業は進んだにちがいない。それをこんどは、プロジェクトの指針も財政支援も同じだろうから、隣りのマルツァーン地区で確かめてみようと思い、まずマルツァーン地区の北端、いま「マルツァーン地中海の風情」をキャッチフレーズにしている「アーレンスフェルデのテラス」を見ることにした。
2019年9月8日の朝、オストクロイツ駅からS7バーンに乗った。日的他は終点、といっても30分ほどで着くはずのアーレンスフェルデ駅である。しかし、この日、その時刻は途中のシュプリングプ-ル駅どまり。ドイツではよくあることだが、その先は定期バスかトラムに乗り換えろとの表示である。すぐ来たバスに乗ってアーレンスフェルデにむかった。もうこのシュプリングプフールあたりは高層住宅群にかこまれ、Sバーンに並んではしるメルキッシェ・アレー沿いにその先は、とくに右側に切れ目なくつづいている。車中から見えるのは、デザインと色彩にそれぞれ変化をみせる高層の人大きな建物、舗装した大きな広場、緑ゆたかな大きな公園ばかりである。乗客は若い人がほとんどで、半数以上が外同籍出身と思われる。バスは、Sバーンと大差はなく20分ほどで終点に着いた。マルファーンの団地群を通り抜け、一気にその全景を眺めた気分である。
マルツァーン地区の大団地建設は、年表をみると、1971年のSED(社会主義統一党)第8回党大会で、76~90年間に280~300万戸を新設および改修する住宅建設計画を73年10月の中央委員会で具体化すると決定し、73年に政治局がピースドルフ北隣りマルツアーン村を中心に76年から35万戸を建設すると決めたことにはじまる。
施主は国営住宅建設企業Staatlicher Wohnungsbau der DDRであった。その第1号が完成したのは1977年12日である。シュプリングプフール駅に近いマルクヴィツア通り43-45の1O階建て住棟である。その後急ピッチに道路・交通の整備とともに開発地域を拡大していった。STバーンでいえば、マルツァ-ン駅からラウル・ヴァ-レンベルク通り駅、メ一ロアー・アレ一駅にいたる広大な地域を「マルツァーン居住地区1、2、3」の名で1989年までに38,332戸を完成させた。さらに80年からその北へ、東へと建設地域を拡大していった。最終的にはマルツァーン地区全域に1990年までに5~21階建て住宅および施設あわせ約62,000戸を建設したことになる。
●アーレンスフェルデのテラス
「マルツァーン」は、区の南端の小さな村の名が団地建設の拡大とともに北上して広域にわたる行政地区名となり、またそれが居住地区の総称ともなっている。その最北端にあるのがアーレンスフェルデ地区である。わたしが歩いたのは、線路沿いのメルキッシェス・アレ一、ハーフェマン通り、ボルクハイダー通り、ヴイテンベルガー通りにかこまれた区画である。
メルキッシェス・アレ-沿いには11~12階の高層住棟が正方形に3つのブロックをつくり、東側の中央部には、6階あるいは8階建て、なかには3階建てもあり、長短の住棟が曲線をなして並列しており、低層の幼稚園や小学校などもある。3階建ては、あきらかに減築、大改造をした住棟である。同地のなかの道幅は狭く、緑ゆたかな植栽、築山があったりして、曲がりくねっている。減築し大改修をしたと思われる中低層の建物が多い区画には高層住棟は見られず、緑地がひろがっている。高層住棟が撤去された跡かもしれない。
もっとも目引くのはベルコニーの改造である。同じ住棟でも減築した階層が階段室ごとに異なり、4階あるいは6階建てになっている。薄い色合いの躯体に後付けされた色鮮やかなベルコニーとその枠、並べられた鉢植えは、明るい雰囲気を放っている。3階建てに減築され、おそらく切断されて短くなった住棟のバルコニーは、大きく外に張り出していて広いスペースを作っており、階段室だけが4倍まであるのは、屋上がテラスになっているのであろう。この低層住棟にはテナント・ガーデンが整備され、高い生け垣にかこまれてプライバシーが守られている。
先にみたように、とくに旧東ドイツの高層大団地は、さしせまった住宅難解決のため1970~1980年代にプレハブ工法で大量建設されたもので、質より量、スピードが求められた。10年もすると高層住宅の魅力は急速に失われ、多くの住民は離れていった。1期7年に建ったばかりなのに、マルツァーン北端のこの団地はドイツ統一後、2000年代になると空き家率30%を記録した。状況は最悪だった。ベルリン市議会は団地リノベーションにもう資金を投じたくない、解体が唯一の解決策と言いだした。
住民、.住宅団体、地区代表たちはこれにこぞって反対した。関係者協議の末、アーレンスフェルデを将来「小さいが、よりよい住宅」をモットーに、野心的な目標をたて、ベルリンの都市再開発プロジェクトに合意した。ベルリン市の住宅建設振輿協会Deutsche Gesellschaft zur Forderung des Wohnungsbaus AG=DcGcWoは、「東の都市改造」の資金援助をうけた。2003~05年に11階建て16ブロックを3~6階建てに滅築した。高さが波うち、屋上にはテラスとしいった雰囲気である。このエリアを「アーレンスフェルデのテラス」と名づけ、「マルツァーンに地中海の風情」Ahrensfelder Terrassen --Mediterranes Flair in Marzahnをキヤ・フレ-ズにした。、
プレハブ構造だから、レゴのようにパネルを外したり、部品を取り換えたりして建物の部分解体、改築、近代化は案外容易かもしれない。室内をすっかり改造してキッチンや浴室を新しくし、バルコニーを改修、テナントガーデンも整備できた。DcGeWo社は48~102㎡の床面債にたいし39タイプのフロアー・プランをもっているという。借り手の少ない5DKなど大型住宅は小住宅に分割された。高層プレハブ住棟は一部撤去され、広々とした緑のスへ-スが生み出された。
わたしが一巡した地区に大きなスーパーマーケットが2店あった。通りに画して店をだしているのはカフェバーや花屋が多く、ハーフェマン過り治いの商店街は40~50メートルもつづく。トルコ料理のファーストフード店でビ一ルを飲み遅い昼食をとりながら、遺行く人を眺めていた。外国籍出身らしい人たちはたしかに多いが、トルコ人がとくに目立っわけではない。安くてボリュームのあるケバブなどが人気なのだろう。マルツァーンの人口統計によると、ドイツ人のほかは、旧ソ連人、ベトナム人、ポーランド人なども多いはずである。
アーしンスフ上ルデのテラスから市内にもどる途中、トラムでアルト・マルツァーンに下車、アレー・デア・コスモナオテンとブレンハイム通りにかこまれた地域を歩いた。18階建ての高層マンションも近くに1棟あったが、11階建て住棟が並列で、あるいは5階建てがコの字型に組み合わさって建っている。3階建ては11階を滅築して大改修をしたのか、バルコニーは張り出していて、塗り色もまだ鮮やかに見える。所有主は住宅阻合フリーデンスホルトWohnungsgenossenschaft Friedenshort e Vである。
どこでも住棟は鍵をもつ入居者か入居者が室内から招く者しか入れなくできている。わたしは玄関パネルをながめ、入居世帯や空き室を数えたり、「チラシの投入お断り」の貼り紙などを見ていた。そのとき外出しようとした老夫婦が玄関ドアを開けたまま、わたしにむかって「どうぞ」といったので、遠慮なく建物のなかに入れてもらった。階段を上下したり、エレベーターで最上階まで行き、緑ゆたかな中庭の植栽や住居の裏側を観察し、中高層住宅群の遠景をカメラに収めることができた。
すでにいくども述べたことだが、ベルリンの大団地はどこでも郊外の、かっては農耕地や沼地、雑木林だったところに建設されたのだろうが、公共交通機関が同時に整備され発達していて、初めての外国人旅行者にも容易に、しかも短時間に行ける点が大きな特徴に思える。市の中心部から遠くても40分以内に行ける。,片道1~2時間もかけて通勤をよぎなくされている東京生活者にはうらやましい限りである。
『住宅団地 記憶と再生』 東信堂
『住宅団地 記憶と再生』 東信堂
地球千鳥足Ⅱ №45 [雑木林の四季]
死の谷、死のスピン
小川地球村塾村長 小川律昭
小川地球村塾村長 小川律昭
ワイフとラスヴェガスで待ち合わせをし、カリフォルニア州のデス・ヴアレー(死の谷)をドライブすることにした。私は成田からラスヴェガスに向かった。飛行機で見下ろすと砂漠に突然灯火の海が現れ、きらびやかなことこの上ない。これもアイデアと財宝投入して.-つの街を造った人間の業、目標意識と行動がセイジ・ブラシ(やまよもぎ)しか育たない砂漠を都会に変化させた際立った例であろう。
空港やホテル、どこに行ってもスロットマシンが設置してある。さすがはギャンブルの街である。フラミンゴ・ホテルに一泊、真似事程度のギャンブルをした。ルーレットで二〇〇ドルを失うのに時間はかからなかった。やり方次第で楽しむことも出来ただろうが、面倒くさくなって賭ける札数を増やしたのは、止める潮時だったようだ。経験することに意義あり、だ。
翌朝セイジ・ブラシ以外何もない荒地を走ること三時間、目的の死の谷に着いた。谷底を走る一本の道を挟んで白っぽい荒地が広がっている。奇妙な形の山肌あり、砂丘あり、乾いた塩の河や渓谷あり、涌き水あり。最北端のスコッティ・キャッスルとバッド・ウオーター問での七五キロに見どころが点在、もちろん、死の谷といえども小部落の民家も存在している。これは鉱山跡の名残であろうか。
中心部ファーナス・クリークから一二マイル地点のストーン・ブリッジを見ての帰りだった。下りのジヤリ道で突然ブレーキがきかなくなった。加速して車が滑って行くではないか。どうしよう! どうして? どうしてブレーキがきかないの? 右足に力が入るが、車はさらに加速するのみ.ああ、横転するぞ。もうだめだ! ああ……。
ハンドルにしがみついた剥郡、轟音とともに車がストップした。 一瞬意識を失っていた。気がつくと、フロント・ガラスがもうもうとした埃で真っ白になり、何も見えなくなった。ああ、何と車が止まったではないか。窓が閉まっていた車の中も攻でもうもうとしているJ何が起こったのか? ここは何処? 車はどちらを向いているのか、何もわからない。ワイフも「死ぬんだ!」と思ったのち意識が失せていた、と言う。
動くかな、とエンジン・キーを回した。エンジンはかかり、アクセルを踏んだら前進した。その時フロント・ガラスの埃が取れた「何と車は逆に坂を上がる方向を向いているではないか。バックして車の方向転換し、さて前進しようとしたら車の前面から埃がドーッと内部に人づてきた。ワイフが「車が壊れたのでしょう!」と叫んだ。降りて調べたら、前輪左側タイヤのホイールとゴム部がはずれ、潰れてジャリの中に沈んでいる。同じ側の後輪もホイールとタイヤ間にジャリが数個食い込みパンクしそうな状態になっている。ようやく状況を把握した。ブレーキがきかなかつたのはローリング現象、スピ-ドとともにタイヤの表面のジャリが、一緒にくっついて回転し、摩擦抵抗が小さくなったせいだろう。さらにタイヤがジャリ道に食い込んで、かなりのジャリがタイヤ内に食い入り、パンクさせたのだろうか。下り坂ゆえ加速も手伝ってハンドルを取られ、スピン{回転)し、それで止まったことがわかった。「駄目だ!」「これまでか!」と剥那に去来した恐怖を思い出しゾーッとした。場合によっては横転を繰り返して車はつぶれ、「死の谷」の名のごとく死への旅立ちとなったに違いない。
さて、パンクだけの被害とわかったものの、これからが大変。タイヤとジャッキを取り出した。アメリカでは初めての体験ゆえ、ジャッキの固定さえ不慣れで思案していたところ、通りかかったジープのおじさんたちが手伝ってくれた。というより、さっさとやってくれてタイヤ交換がほどなく終了。日本のスナック数袋を咄嗟にワイフが差し上げた。アメリカに住んでいたワイフのために日本から持参して車につんでいたものだ。おじさんたちはニコニコと手を振って走り去った。この出来事は我が運転生涯初めての経験であったしあのような恐怖の一瞬では理性も判断も利かない、ということを知った。ただ、運だけで救われた。神のご加護で「生」をいただいたと感謝した。
ショックから覚めやらなかったが、途中、死の谷きっての景観地、ダンテス・ヴュー見学を抜かすわけにはいかない、とワイフが言い、上通路から外れること一三マイル、標高一六六五メートルの高地に向かった。標高差一〇〇〇メートル、夕暮れ時に上る車は私たちの一台のみ、もう七時近くですれ違う車は一台もない。二人とも心細さほひとしおながらも口に出きず、遅い時間を気にしながらなんとか頂ヒの見晴らし場に着いた。それでも三台の先客の車があった。とっくに日は沈み、山陰からの残照に映える紅色の雲の美しいこと。見晴るかす裾野には谷を埋め尽くす塩の河があった。白く浮き立って薄暗い山間と調和し、表現しきれぬ雄大な光景、死のスピンからの生還と、静寂の中のスペクタキュラーな大自然を短時間のうちに経験し、言葉にならない感動で立ち尽くした。立ち去りがたい余韻に後ろ髪をひかれつつそこを山発した。
一路帰路へ、あとは、カー・ジャツクに怯えながら、左右にくねった道を暗闇の中一気に下山するのみ 二人とも心中の複雑な興奮と緊張で身を固くし言葉少なであった。
その日モーテルに落ち着いたのは九時過ぎ、田舎のカジノを兼ねたレストランで、無事であったことに乾杯した。人間の生命とは宿命づけられたものがあるのだろうか。
(一九九六年十月)
『地球千鳥足』 幻冬舎
『地球千鳥足』 幻冬舎
山猫軒ものがたり №37 [雑木林の四季]
小屋を建てる夢 1
南 千代
南 千代
龍ケ谷のみんなは、うちとけてくると、
「よくこんな所に住む気になったなあ。ここは、私らでも龍ケ谷のチベット、と呼んでたくらいでよ。ここらでもー番、陽があたんなくて寒い場所だかんな」
と言った。そして、
「冬の問だけでも陽があたる所に小屋でも建てて、寝起きしたらどうだい」
と、すすめてくれた。
十一月も勤労感謝の日を過ぎると、山猫軒の屋内はすっかり冷え、冬場の室温は零下五度ぐらいになる。家の前の通も凍る。冬は、ギャラりィもさすがに休みにした。
ほんとに、暖かい小屋があるといいな。ひと部屋でかまわない。簡素なべリドに薪ストーブ、小さなテーブルをひとつだけおこう。窓もつけよう。朝は、キリリとした水のように冷たくおいしい空気と、光のおしゃべりで目覚めることができるだろう。l
ストーブで沸かした湯でコーヒーを入れ、.パンを焼いて食べる。それから山猫軒にもどれば今まで通りだ。この想像は、まるで隠れ家造りを企んでいるときのように私たちを楽しくさせた。私は、想像することが大好きだ。それだけで、楽しくなれる。ずっとずっと想像していると、それはほんとにカタチを創ってしまう気もする。
長い夜。夫がテーブルの上で厚紙の小さな家を造っている。
「ぼく、小屋を自分でコツコツと建ててみようかな。土地はどこかに借りてさ。食べ物はほぼ自給できるようになったから、次は家だ。材料になる木さえ手に入れることができれば、何とか建てられると思うんだ」
ちょうどその頃、梅本のコーさんが古くなった家を新築した。聞くと、自分の山の木を材料に使ったこともあるが、かかったという費用が驚くほど安い。一軒の家で数百万円なら、私たちの冬場だけの小屋は、もっと気軽な金額でできるだろう。親から継いだ財産な幸いにも私たちには何ひとつなく.家を建てるなどとは考えたこともなかった。が、夫はキコりたちと親しくなるうちに、また、コーさんの話を聞くうちに、それなら、自分にも何とかなるのではと思い始めたようである。
問題は、貸してくれそうな土地だ。小沢さんに相談に行った。小沢さんもあちこち心あたりを捜してくれるという。場所が、見つかった。龍穏寺から東へ両を越えて、同じ龍ケ谷でも、小沢さんが住む戸神へ向かう途中、山猫軒から約一・五キロの地。山の中の楊たまりに、土地を借りられることになった。
土地の字(あざ)名は、奇しくも「南」。すぐ積には南川という渓流も流れている。
自分たちの手で建てることに決めはしたものの、さて、どう建てるか。夫は、一番簡単に手造りできる家、というとやはり丸太小屋だろうか、と思案している。丸太小屋 ― いわゆるログキャビン? 材料に、木を使いたいことは変わらないが、ログキヤビンというのも、どうもイメージが違うような気がする。
靴をはいたままで生活するログキャビンの暮らしならよいけれど、多湿である日本の気候風土では、農家の土間ならともかく、室内の床の上を土足で歩く生活は難しいのではないだろうか。雨の日など、靴の裏が、とうしても大量の泥を部屋の中に持ち込んでしまう。
もっとも、市街地や整備された別荘地のように、周囲や退路がコンクリートで固められている場所に建つログキャビンは、この場合、全く別の世界である。
家を一歩出たら土である環境のログキャビンでは、どうしても屋内に入る時は、靴を睨ぐことになるだろう。そしてスリッパに履きかえ、また、じゅうたんの上ではスりッパを脱ぎ、こたつに入ってみかんを食べながらテレビを見る……。普通の家でなら何とも感じないそんな暮らしも、これがログキャビンの中での生活となると、想像していて何だかちぐはぐな気分になるのは、私だけだろうか。使いもしない暖炉や薪ストーブが、家の中にインテリアとして飾ってあるのを見かけた時も同様の気分になってしまう。
では、どんな木の家がいいのかとなると、やはり、寝起きできる場とストーブがある小屋というだけで 例にあげることができるような、具体的な建物が出てこない。
私たちは、隣の集落である黒山に住む高橋さんに相談に行った。高橋さんは、身障者用の椅子などを造る木工家である。三宅島で行われた木造伝統工法による家づくりの、図解書の作成作業を終え、この地に帰ってきたばかりであった。何かよいアドバイスが受けられるのではないかと考えたのである。高橋さんは、れい子さんの夫だったので、私たちも幾度か会ったことがあった。
『山猫軒ものがたり』 春秋社
『山猫軒ものがたり』 春秋社
BS-TBS番組情報 №302 [雑木林の四季]
BS-TBS 2024年4月前半のおすすめ番組
BS-TBSマーケテイングPR部
BS-TBSマーケテイングPR部
御社の乱れ正します!

4月2日(木)よる9:00~9:30
☆BS-TBSドラマがゴールデンタイムに進出!不倫カップルを断罪する人気漫画を実写化。
<キャスト>
三枝 玲 … 山崎 紘菜
鹿妻 新 … 飯島 寛騎
ガンちゃん … 小笠原 海(超特急)
ほか
#1
「オフィスAIRクリーニング」の社長・三枝玲は、周囲に迷惑をかける社内不倫の当事者たちを鮮やかな手口で別れさせる社内不倫別れさせのプロ。玲に別れさせられない不倫カップルはいない!
今回の玲の仕事は、イベント会社で社内不倫を行う妻子持ち課長・槇原と若くて可愛い女性社員・梨々香を別れさせること。玲は地味な派遣社員に扮して、イベント会社に潜入する。梨々香は全く仕事が出来ず、彼女が起こしたトラブルは、他の社員に多大な迷惑をかける。しかも、梨々香の肩を持つ槇原課長によって、トラブルの責任は梨々香に仕事を教えていた高橋さつきが取らされることに。あまりの理不尽さに涙を流すさつきのもとに玲が現れる。「社内不倫は排除されるべき迷惑行為です。誰かが別れさせてくれるといいんですけど...」と意味深な言葉を残し去って行く玲。玲は、仲間の鹿妻新、ガンちゃんに対し、「クリーニングを開始する!」と宣言。玲は美しく変身すると、槇原課長に、偶然を装って接触を図るのだった・・・。
関口宏の一番新しい江戸時代


4月5日(土)ひる12:00~12:54
☆日本の礎は<徳川260年の歩み>にあり。古代、中世に続く最新シリーズ!
~江戸時代~#101「江戸時代の始まり『天下泰平』へ家康の構想」
・徳川家康 鉱山を直轄地化、貨幣を鋳造へ
・家康が江戸幕府を開く
・家康が息子・秀忠に将軍職を世襲→大御所政治へ
・利根川東遷が始動
・「禁教令」公布
出演者:関口宏、涌井雅之(造園家・東京都市大学特別教授)、田中優子(法政大学名誉教授、江戸文化研究者)
薬丸マネー塾~人生後半お金に好かれる生き方~

4月5日(土)よる6:30~7:00
☆お金に好かれたい人は必見!薬丸裕英と一緒に学ぶマネー塾。
<キャスト>
司会:薬丸裕英
進行&リポート:御手洗菜々(TBSアナウンサー)、南後杏子(TBSアナウンサー)
#1「新NISA」
御手洗アナウンサーが今年から始まった「新NISA」を調査。お金の賢人として登場するのは、「家計の見直し相談センター」代表の藤川太、家計と健康、介護福祉に詳しいファイナンシャルプランナーの黒田尚子、「プレジデント・オンライン」編集長の星野貴彦。
海の見る夢 №74 [雑木林の四季]
海の見る夢
-Highway Star-
澁澤京子
~最も人道的な人々は革命を始めません。彼らは図書館を始めます。
~『わたしたちの音楽』ゴダール
一日中、遠くからサイレンの音やヘリコプターの音が聞えていた。終礼の時間に、まだ興奮を隠せない若い担任の女の先生が三島由紀夫の自決を告げたのは、中学一年の秋だった。
70年代は三島由紀夫の自決と共に始まった。そのころ、Gパン屋に入るとお店のBGMによく流れていたのはディープパープルで(昔のGパンは藍の染料の匂いがした)、本屋に行くと新潮文庫のサルトルが充実していて(背伸びしてサルトルやジャン・ジュネを読んでいた)「なんでも見てやろう」小田実、「書を捨てて街に出よう」寺山修司、「見る前に跳べ」大江健三郎など、やたらと「行動」を呼び掛けるタイトルの本が多かったのを覚えている。同級生と銀座の映画館で「燃えよドラゴン」を見て衝撃を受けたのも70年代だった。
実家の本棚にあった三島由紀夫の「午後の曳航」を読んだのは小学校高学年の時。それから家にあった三島由紀夫の本は夢中になって片端から読んだ、三島由紀夫の本は、思春期の自意識の不安定な時期にしっくりとしたが、三島由紀夫ほど「観念的」と批判される作家もいなかった。三島由紀夫にはチェーホフのような恋の哀しみと滑稽さは書けなかったと思うし、三島由紀夫の好きなダヌンツィオの『死の勝利』のような、腐れ縁の男女関係のどうしようもなさも書けなかっただろう、出征した丸山真男の『超国家主義~』の底辺に流れるやり場のない怒りも、彼の経験したことのないものだった。『三島由紀夫VS東大全共闘』は、三島由紀夫自身の育ちの良さと、誠実な人柄がよくわかるドキュメンタリー映画だが、彼は、早熟な天才少年の心のままこの世を去ってしまったのではないだろうか。
70年代は「肉体」「暴力」という言葉がやたらと氾濫した時代だった。東大全共闘の芥正彦氏と三島由紀夫の対話で、芥氏が、(我々を束縛する)イメージ・観念を乗り越えるための(空間・時間からの自由)を主張するのに対し、三島由紀夫はあくまで国体(天皇)を目指すのである。三島由紀夫があくまで「絶対」を希求しアイデンティティのよりどころを求めていたのに対し、世界をドラマツルギーとして見る演劇人である芥氏は「絶対」などは存在しないという相対主義の立場。常識や既成観念をひっくり返し、人に不安を与えたい」と三島由紀夫は語っていたが、それは全共闘もまた目指しているものであった。しかし、人は自分の価値観からそんな簡単に自由になれるものではなく、無意識状態になれば、ほとんどの人が自分自身の(習慣や価値観の)奴隷になっているのである。
肉体というのは混とんとした理不尽なものである、三島由紀夫が横尾忠則を高く評価したのも、初期の横尾忠則の絵には日本人の泥臭さというものがかなり意図的に描かれていたからだ。柳田国男がブームで、東北旅行がしきりと宣伝(そのころのJRの中吊り広告)されていたのも70年代だったし、やくざ映画や任侠ものの流行も70年代だったと記憶している。藤圭子「夢は夜開く」が大ヒットし、日本人の原点は東北や演歌、任侠モノにありといった時代風潮があり、まだ貧しさの残る日本の風景を、ノスタルジックな美しさとして描いたのはつげ義春だった。かつて永井荷風が向島を逍遥したように、生活感のある風景が徐々に日本から失われつつある時期だったのだと思う。
「荒野にて」という三島由紀夫のエッセイに、ある晩、頭のおかしくなった三島ファンの青年がガラスを割って家に侵入してきたという話があって、その青年がまるで自分の無意識からやってきたような気がした、と書いてある。人の無意識は荒野のようなもので一体、何が潜んでいるのか本人にもわからないと締めくくってあって、昔、そのエッセイがとても印象深かったので覚えている。
ニーチェが好きで、弱者のルサンチマンが嫌いだった三島由紀夫は、学生運動の時代を「女子供の時代」といったが、観念→行動という観念的である点で三島は全共闘に親近感と愛情を持っていた。三島由紀夫が最も嫌ったのは、今の世の中にもたくさんいる冷笑主義者で、変に醒めたことを言ってマウントを取り、それを「知的」と勘違いしている人々(ネット右翼に多い)。三島由紀夫は今の、うそとごまかしで「美しい日本」を掲げる、右派政治家たちをどう思うだろうか?お金に汚い今の議員や、三島由紀夫の大嫌いな「寄らば大樹の陰」「集団化」を好むネット右翼をどう思うだろうか?都合の悪い情報はフェイクと決めつけ、平気でデマを垂れ流し、(これが正直だ!)といわんばかりに、パフォーマンスとしての差別発言を行う右派の政治家たちをどう思うだろうか?
~心を空にせよ 型を捨て形をなくせ 水のように~
~良き人生は過程であって、結果ではない。方向性であって目的ではない。~
ブルース・リー
三島由紀夫と東大全共闘の対談に出てくるのが「認識・肉体」「言語・肉体」の一致についてで、三島由紀夫の認識(言語)→肉体とは全く逆のコース、肉体の鍛錬によって、肉体→認識に至ったのが、ブルース・リーだった。三島由紀夫が常に「死」「無」を意識していたのに対し、ブルース・リーは常に「生」を生きていた。ブルース・リーの映画を見て衝撃受けるのは「こんなに美しい身体の動きがあるなんて・・」という驚きであり、実際ブルース・リーはダンス大会でも優勝している。その流れるような体の動きと言い、ブルース・リーは天才的な身体感覚を持っていた。十代の時にボートを漕いでいて、オールで叩いても水は傷つかないことに気づき、忽然と武術の本質がわかったというのだからすごい。老荘思想というのは本来、身体感覚で「理解」するものなのかもしれない。子供の時から喧嘩が強く不良だったブルース・リーは、武術を習うことによって徐々に変わってゆく。そして32歳で突然死するまで、修行僧顔負けのストイックな肉体の鍛錬に励んだ。もし突然死がなかったら、ブルース・リーはその後、瞑想家になっていたんじゃないだろうか。作家だった三島由紀夫が切腹自殺したのに対し、格闘家だったブルース・リーは逆に精神の中に静かな場所を発見していた。そして、二人とも「唐突に」この世から姿を消した。
三島由紀夫のボディビルで鍛えられた肉体、ブルース・リーの鍛錬された無駄のない肉体。彼らの盛り上がった筋肉を見ていると、肉体というのはなんて孤独なものだろうと思う。「全共闘VS三島由紀夫」の冒頭で「他者」の問題が出てくる。他者、そして自分の肉体の「モノ化」がエロティシズムと暴力の始まりなのである。しかし「肉体」の鍛錬から精神的な境地に至ったブルース・リーからわかるように、「肉体」そのものに問題があるわけじゃない、問題は肉体の「モノ化」なのであり、肉体のモノ化、人のモノ化は結局、今のイスラエル政府や、あらゆる国の分断と残虐、セクハラ問題までつながってゆくだろう。
三島由紀夫は自決せずに、肉体→精神のプロセスをたどり、もう一度作家に戻ったほうがよかったんじゃないかと思う・・
インターネットの登場とともに、ますます肉体のモノ化(自他含めて)はひどくなり、同時に言葉(知性)の劣化も始まった。自分自身や他人を単純にキャラ化したりカテゴリー化して安心し、人の無意識の深さと複雑さは尊重されるどころか闇に葬られるようになった。言葉というのは安易に使えば多様性を抹殺するが、同時に言葉は世界の多様性に対して開かれるものでもあると思う。物語が延々と紡がれてゆくのはそのためなのだ。
パレスチナ問題を扱ったゴダールの映画『わたしたちの音楽』には、イスラエルに暗殺された詩人ダルウィーシュの話が出てくる。詩は暴力より強いのか?と映画は問いかける。イスラエルが真っ先に爆撃したのがパレスチナの大学と病院だったが、イスラエル政府が恐れているのはパレスチナ人の知性であり、これから大人になる子供たちなのだろうか?今のパレスチナ停戦デモは60年代の学生運動とは全く違う。むしろ、警官の警備のほうが強制的で暴力的に感じるほどで、「暴力肯定」の全共闘世代のデモと違うのは、革命ではなく是正を目指すからだろう。今は、「人に不安を与えたい」と三島由紀夫が語った高度成長期の70年代のように「安定」した時代じゃなく、イデオロギーというものも消失し、日本経済の落ち込みや異常気象などでむしろ私たちは、「安定」した日常を脅かされている時代に生きている。異常気象が世界中に影響を及ぼしているのと同じように、アメリカやパレスチナで起こることは、同時にどこの国でも起こりうる、というグローバルな時代。憲法を改正したところで日本の軍隊はアメリカの指揮下だろう。そして、今の時代の「反知性主義」は70年代の「肉体の復権」「混沌」などではなく、もっと劣化したものであって、何でも単純化することにはじまって、野蛮な差別や分断と排外主義、ヘイトスピーチという言葉の暴力なのであり、それは人間性の喪失と野蛮への退行だろう。
今の時代に必要なのは、むしろ繊細な感受性を伴った「言葉の復権」、つまり「知性」ではないかと思う。知性を持つということは、他人の痛みに対して敏感な身体感覚を持つ事であり、他人に耳を傾けることであり、世界に対してオープンな心を持つ事であり、また、世界の理不尽に対して目を閉じないことだろう。少なくとも書物、映画や哲学、文学や芸術は、世界も人もそんなに単純なものではないことを教えてくれるだろう。
住宅団地 記憶と再生 №32 [雑木林の四季]
ベルリン・ヘラースト地区の団地
国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治
団地再生への公的資金と当事者全員参加
あえて特記するならば、団地の大規模改修にたいする住民の協力態勢と事業の進め方についてである。
既存住宅を住民が住んだままの状態でここまで大規模に改修するうえでの住民の協力態勢づてりは学ぶべきだろう。住宅の所有形態は、おそらく買付が多く、管理者は単一組織ではないだろうから、団地改造を円滑にすすめ、再生を実現するには、計画段階から住民の参加、自治体をはじめ管理主体と建設会社、専門家等による協議と合意、それに公的資金の援助が不可欠である。そのプロセス、とくに住居および屋外改修にたいする住民の参加と裁量について詳細に知りたいところである。
それに元々が社会主義体制のもとでの国営であり、ベルリン市に移管され、管理が民間組織に託されても、まだ民間資本の所有に分断されてはいまい。その背景が、利益本位の介入を許さず、関係者合意を進めやすくしていると思える。そのうえ、さきにも紹介した順重な都市更新のための12の原則」に象徴される基本の徹底である。団地再生への当事者全員参加、維持保全と改造の優先、公的資金の投入などの原則が実施に移されていった。こうした背景があり条件が保障されていてこそ、団地再生も進み、ひろい意味での国民資産の保護向上が実現するのであろう。
さらに、へラースドルフの団地再生事業の理解を深めるために、あらためて「ヘラースドルフ・プロジェクト」と「へラースドルフとマルツアーン」地域の2点について補記しておく。
◇ヘラースドルフ・プロジェクト
1981年に大団地建設をはじめ、10年後には建物の劣化、、住環境の不備が露呈していた。東西ドイツが統一して91年にベルリン市は、へラースドルフ全域の団地について、ヘラースドルフ住宅建設会社“Wohnungsbau gesellschaft Hellersdorf mbH=WoGeHe、その他パートナー企業とともに団地改修計画にのりだした。92年から94年にかけて6つの戦略のもとに各地区に固有の多様なモデル・プロジェクトを設定した。その実施にあたっての重要な前提として、目に見える形で住民に「団地改修が始まった」「住みとどまることにしよう」と思わせる必要、住民・行政・事業者の共同協力の必要、生活条件改善の長期的な目標と計画を明示する必要を指摘している。戦略の概要はつぎのとおりである(WoGeHe:The Hwllsersdorf Project)。ちなみにこれらは、都市計画の目標および計画作成にあたって考慮すべきと建設法典(2004年改正)が定める衡呈事項に対応している。
戦略1:環境に配慮した住戸の近代化―9一雨水、太陽光の利用とごみ減量、ファサード、バルコニー、窓、玄関、階段室の改修、エレベーターの付設、住んだままでの工事の計画づくりをあげる。
戦略2:居住階層、ニーズの多様化に対応する魅力の創建とソーシャル・ミッゥスの維持一一DIYをふくめ室内改修、バルコニーの拡張、都会生活と緑の享受、所有形態の多様化をかかげる。
戦略3:都市機能をはたす都市センターの創出一―1992年の国際コンペにより、アリス・サロモン広場を中心にショッピング街だけでなく、医療・教育機関もあわせ、市民ホール、遊園地、アイスリング、緑の公園等をつくる。
戦略4:生活水準と生活の質の改善一一若者にスポーツ施設、中高年に集会所の建設、野外映画会の開催・コミュニティの形成とともに砂漠から緑のオアシスへ,テナント庭園で「緑のリビング・ルーム」をめざす。
戦略5:大団地を自然の領域に統合――バルコニーと庭園の連結ビオトープ、グリンベルトの形成、動物保護、自然保護と環境教育の推進をはかる。
戦略6:計画実施は民主的に一―大団地の開発方針は住民の生活に直接影響をおよぼす。計画づくりには、まず住民の日常生活上の経験と意見を吸収し、それを行政、建築家、事業者の専門知識につなげる(住民は計画プロセスの最初から参加し、決定結果をうけいれる。住民参加なしの計画はありえない。くわえて、その地域の歴史をたどり、地域道産を活かす。
『住宅団地 記憶と再生』 東信堂
『住宅団地 記憶と再生』 東信堂
地球千鳥足Ⅱ №44 [雑木林の四季]
原発の国で夫婦下痢道中
~ウクライナ①~
小川地球村塾村長 小川律昭
小川地球村塾村長 小川律昭
乗り継ぎて立ち寄ったモスクワはセレメチーボ空港で会った日本人団体が、「あなたは何のためにウタラィナに行くの? 観光の見所は何もないよ!」と言った。彼らには日本人夫婦のウクライナ・バックパックの旅は珍しかったようだ、「旧ソ連邦から独立した諸国を旅している」と告げたが、「他にはもう行く国が少ない」とは言わなかった。彼らは26年前のチェルノブイリ原発事故の跡を辿り、その後遺症で病んでいる人たちを見舞うため、金品を携えて来た団体だった。福島原発事故後の参考にする調査か、東北方面の人が多かった。「予約がないと事故現場周辺には行けない」と知らされた。旧ソ連邦から独立した発展途上の国ウタライナ、西欧寄りなのか入団にビザも不要で、街も新旧の建造物が入り交じって調和していた。人々は開放的で明るい。街を闊歩している若い女性やビジネスマンは垢抜けのした服装でスマートきが感じられた。しかし商店では旧共産圏の名残か笑顔が乏しく無表情、「売ってあげる」態度でサービス業に徒事している人たちを見かけた。道端で手を差し出す人は僅か、秋に首都キエフでサッカーのヨーロッパ遣手権が開催される。
旅人に不便だったのは道を訊いても逃げられてしまうことだ。日本もそうだが英語が喋れぬ人が多いのか、観光客に慣れていないせいもあるだろう。ホテルのボーイが黄金の門街の正面玄関への行き方を遠回りで説明してくれた。多分英語が聞き取れず他の建造物と間違えたのだろう。坂道の多い街で徒歩の観光には限界を感じたが、やたら歩いたお蔭でキエフ最古の教会、世界遺産のソフィア太聖堂を見ることができた。頂上の塔が鮮やかな緑と黄金色で彩られた派手な建造物だ。「有名なロシア正数の殿堂ペチュールスカ大修道院には「聖」と「俗」とが共存する。広大な敷地に由緒ある教会の逸物群が配置されており、内部の壁画はフレスコ画で埋め尽くされている。市内の見学は3路線ある地下鉄を利用したのだが、地底への深さが2段階に分かれて100メートル以上もあるエスカレーターだ。スピードは早く、騒音は大きい。車内は混んでいる。ソ連時代の遺産だ。
ウクラィナと言えはキエフ郊外のチェルノブィリ原発事故だ、今になって関心が山たのか博物館で日本人の医者グループの団体に会った。後遺症とその対応状況を調べるためのようだった。館内は写真中心、亡くなった子どもたちの顔写真や防護服をつけた係官の作業婆だけ。事故後3日経ってソ連の調査団が入り住民たちに事件を知らせたという。当時の状況は闇の中、徐々に被害状況の恐ろしさがわかって海外に脱出した人たちもいた。シンシナティでチェルノブィリから避難して来た一家に会ったが、将来を熟考して避難したのだろう。
元気だったワイフがダウンした。前夜の寿司が原因か。食事を絶ってホテルで2日間安静にした。体力が疲弊した頃にやってくる病気だ。生野菜には気をつけているのだが運の悪い時はこんなもの、彼女はどの同に行っても下痢を止めるのに寿司だ。寿司はおまじないみたいに腸を回復させるのだが、初めての逆効果だった。次の街リヴィウでは私も同じ下痢でダウンした。ホテルで食べたステーキ肉かその付け合わせか。同じように絶食で下痢に耐えた。薬は現地で調達したほうが症状に合うと その都度買い求めて服用する「レセプションで薬の有無を問い含わせたら、キエフのホテルでは近くの薬局の場所を教えてくれただけ。リヴィウのホテルでは4錠無料でくれた。同じ四つ星ホテルでも対応が異なった。アルゼンチンのコルドバでは医者を呼んでくれて無料だたことを思い出した。優雅な中世見本の街、リヴィウで1日半寝ていたのは悔しい.リヴィウは中欧の古都、旧市街地はリノック広場を中心に石畳の広がる古風で優雅な街並みだ。中欧の「埋もれた宝石」とガイドブックにあるが、徐々に脚光をあびつつあり、ぶらぶら歩きには快適だ。
(旅の期間:2012年 律昭)
『支給千鳥足』 幻冬舎
『支給千鳥足』 幻冬舎
山猫軒ものがたり №36 [雑木林の四季]
焔 2
南 千代
南 千代
ギャラリィを始め、たくさんの人が集まるようになると、山猫軒の台所もこれまでのようにかまどにつきっきり、というわけにはいかない場合も出てきた。かまどに加えてプロパンガスを入れることにした。
ガスレンジを入れ、スイッチをひねる。ポオ!と青い炎がつく。すこい、つまみをひねるだけで、一秒だけで火かつくなんて!いいのかしら。私は、ほんとに感激してしまった。 炎は、匂いも煙もなく、赤くもなく、ちょっとすました顔をして整然と燃えている。火の大木さの調整も、つまみの回し加減ひとつで、ずっと思いのままに保ってくれる。かまどの火が、田舎の元気な強い子だとすれば、ガスの火は都会の洗練された賢い子。
両方の暮らしを併せ持つことで、洗練された強さで元気に賢く、暮らしていければよいのだけれど。
丈二さん、伊野さん、清太郎さん、自由の森学園の子どもたち、佐藤さん、笠原さん、などなど。二度目の田植えは、新しくできた大勢の友人たちも加わり、にぎやかにあッという間にすんでしまった。田植え仕事というより田植え遊び。みんな元気な、泥ん子たちになった一日。
「ああ気分がスッキ目したわ。ずっと家に閉じこもって制作してたから、少し体の調子が良くなかったのよ。自然の中で体を動かすって、いいなあ」
笠原れい子さんが言っている。彼女は、同じこの町に住んでいる彫刻家である。
夏の合同展の後、秋は、彼女の作品展であった。仮面を作る彼女が、作品展の最中に言った。
「私ね、こうして作品を展示するだけでなく、実際に仮面をつけて扮装して、一度でいいから外を、町を、歩いてみたいのよ」
作家の意図が何なのか、私は彼女ではないのでわからないが、私は私で、その提案をおもしろいと思った。仮面をつけることで、ふだんは自分の顔に囚われている自分の、ほんとうの顔を見いだすことだってあるかもしれない。それに何だか、楽しそう。
さっそく、やることにした。しかし、まだセブンイレブンさえないこの町で、ある日、ある時、突然に、町の中を異様な仮面の集団が練り歩いたら、人騒がせになるかもしれない。
囲炉裏端でみんなで腕組みをしていたら、利治さんが回覧板を届けにきた。十一月三日、越生町の文化祭とある。これだ。この日に乗じてやれば、「文化祭の催し」になる。誰も不審には思わないだろう。コースは、越生梅林前から、町役場まで。
私は古い時代がかった着物や仮面を用意し、その日を待った。夫は、宇宙人のような銀色のコスチューム。歩行訓練ができているガルシィアも参加させることにして、紫色の風呂敷に銀の水玉を貼りつけて、素敵なマントを作ってやった。
当日。祭日なので、ギャラリィにはお客さまもいっぱい。そろそろ扮装の支度をと、集まった仲間たちと着替える時になって、夫と私はハタと気づいた。ギャラりィは誰が預かってくれるのか。やむなく、私は残ることになってしまった。
れい子さんをはじめ、都内から来てくれたまゆりさん、飯能から参加したダンサー、町の北村きんに長谷部さん、音楽隊の井野さんにサックスの林栄一さん、など。総勢十五人。それぞれに、大根娘やスケアクロウなどと称しながら山猫軒を出発。みんな、私の分まで楽しんでね。ガルシィアも軽トラりクに乗り込み、マントをなびかせながら町に去った。 夜は、山猫軒でパーティーの予定だ。俳優座養成所の小笠原さん、美術評論家のヨシダヨシエさんなど、夜の参加組を迎えながら、私は一行が戻るのを待った。
しかし、遅い。何かあったのだろうか。ようやく、みんな帰ってきた。楽しそうに疲れている気配だ。ホッとしたところに、夫がそばにきて小声で言った。
「ガリシィアが、いなくなったんだ」
役場の広場で行われていた吹奏楽の、シンバルの音に驚いて走り出し、姿が見えなくなったと言う。私が悪かった。可愛そうなガルシィア。参加させるんじゃなかった。
「途中で僕は抜けて、ずいふん捜し回ったんだけどね。参加してくれたみんなの世話を放り出して、犬を捜し続けるわけにもいかないがらね。みんなも待たせていると思ったし」
夫はそう言い、交替して捜しに行くと言った私に、
「大丈夫だよ、また明日の朝早く、捜しに行くから。きっと役場の裏の山に逃げたんじゃないかと思うんた。それより、早く。乾杯をみんな侍ってるよ」
と続けた。乾杯。即興で歌う人、踊る人。パーティー1は盛り上がっているが、私は笑って話を聞きつつもガルンィアのことを思うと、後悔と心配でたまらない。動物まで巻き込むんじゃなかったなあ。電話が鳴った。
「役場の者ですが。お宅で、今日パレードに出てた犬が、広場に坐ってじっと待ってるようなんですがね。引取りに来てくれますか」
あわてて迎えに行った。人影ひとつなくなった役場前の広場。街灯が、マント姿のガルシィアの長い影を作っていた。
「シンバルがバァーンって鳴ったの? びっくりしたね、ほんとにごめんね」
帰ってきたガルシィアが土間に、安心して寝そべっている。薪ストーブの炎が、燭台の蝋燭の炎が、トロトロとみんなの横顔を包み、チクタクチクタクと振子を揺らす柱時計の音が、笑い声が次第に遠く伸びていく。
窓の外には、しんとして白い月。群青色の空を、群れ飛ふ烏のように木の葉が渡っていく。外は、風が強いのだろ。しかし、ここは暖かい。友達、夫、ガルシィア、みんな、みんな温かい。
『山猫軒物語』 春秋社
『山猫軒物語』 春秋社
BS-TBS番組情報 №301 [雑木林の四季]
BS-TBS 2024年3月後半のおすすめ番組
BS-TBSマーケティングPR部
新時代の歌姫!丘みどり熱唱SP~演歌・ジャズ・洋楽からJ-POPまで


3月19日(火)よる9:00~10:54
☆令和の歌姫、丘みどりのコンサートの模様を余すところなくおとどけ!
天才民謡少女として注目を浴び、高校生でアイドル歌手デビュー、さらに演歌歌手と再デビューして開花したその歌人生は今、あらゆるジャンルの作品を歌いこなす歌姫として結実している。
日本全国津々浦々の大ホールでのコンサートも満員にする人気の丘みどりが、昨年初挑戦した都心のライブハウスでの公演。
そこでは、日本のポップスや洋楽をはじめ、実力を問われるジャズやシャンソンまでを見事に歌い上げ、耳の超えた観客に真っ向勝負を挑んだ。
この番組では、ボーカリスト・丘みどりを堪能する、この特別なシークレットライブに加え、プラチナチケットと言われる王道演歌の大ホールコンサートの模様、さらには彼女の歌人生を追うVTRとを合わせて、令和の歌姫の実力と魅力を紐解いていく。
憧れの地に家を買おう


3月22日(金)よる10時~10時54分
☆物件購入を本気で考える武井壮が、世界移住を夢見るゲストと夢を語ります!
#67 ベトナム・ホーチミン
今回の憧れの地は、ベトナム・ホーチミン。東洋のパリと呼ばれる古い建築と高層ビル群が同居する活気ある商業都市。最初に紹介されたのは、ヨーロッパのような美しい街並みの中にある、ラグジュアリーな4階建てタウンハウス。グランドピアノが置いてある4階の部屋は他の階より天井が高く、インドシナ風建築によく見られるドーム型天井です。ジム、屋外ラウンジ、テニスコートまで共用施設が充実。次に紹介する物件は、現在建設中の新しい街に建つお手頃物件です。日本のマンションよりも窓が大きい為、部屋全体が明るく、広く感じられる造り。ホーチミンに移住した日本人は、YouTuberとして活動し、映画にも出演している人気者。最後に登場する物件は、エンタメ満載のリゾートアイランド、フーコック島にある、プライベートビーチ付き物件。ヨーロッパ風の内装でオシャレなシャンデリアが使用されています。
MC:武井壮 ゲスト:三浦大輔
こども音楽コンクール


3月30日(土)よる11時~11時30分
☆“音楽を身近に楽しむ”というコンセプトのもと、1953年にスタートした小学校・中学校が対象の音楽コンクール。
今年度はコロナ禍の影響が色濃く残る中、全国949の小・中学校から2万1053人が参加。小・中学校それぞれ6つの部門(重唱・合唱・重奏・合奏第1・合奏第2・管楽合奏)で「文部科学大臣賞」受賞校が選出されました。
「文部科学大臣賞」受賞校と「審査員特別賞」受賞校には、
3月2日(土)、東京オペラシティ コンサートホールで行われた「文部科学大臣賞授賞式・記念演奏会」で賞状が授与されました。番組では当日の模様をお送りします。・
・・・・・・・・・・・・・
海の見る夢 №73 [雑木林の四季]
海の見る夢
-柳宗悦のラブ・レター―
澁澤京子
アインシュタインとフロイトの往復書簡『人はなぜ戦争をするのか』で、アインシュタインの質問に対し、フロイトは戦争を抑制するものとしてまず「文化」を挙げ、「知性を強めること」と「攻撃本能を内に向けること」が人にとって最も重要であると答えている。昔、この本を読んだときはピンとこなかったけど、ヘイトスピーチ、差別と暴力のあふれる今読み返してみると、フロイトの言っていることは実に正しい。
飢餓状態に追い込まれ、やっと届いた小麦粉に群がったパレスチナ人を撃ち殺す(100人以上が亡くなった)イスラエル兵士の残虐な行動と、ヘイトスピーチに共通するのはまさに「知性の欠如」と外に向けられた「攻撃性」以外の何物でもない。今のイスラエル兵士が、まるでターミネーターのような非情さを発揮し、ヘイトスピーチが虚勢や嘲笑の形をとるのは、彼らが人を見下すことによって、辛うじてあるかなきかの己の優越心を保とうとするからだろう。(それが集団化すると暴力に)逆に今のパレスチナの人々が、優れた人間性を見せるのは、民族性もあるのかもしれないが、彼らがすべて奪われた無防備な状態に置かれているからではないだろうか。
それでは「知性」とは何だろうか?
・・・日本が神の国において罪深いものとして見られる事は、私の忍び得ることではない、私は日本の栄誉のためにも、我々の故国を宗教によって深めたい。私は目撃者ではないとはいえ、様々な酷い事があなた方の間に行われたのを耳にする時、私の心は痛んでくる。それを無言のうちに堪え忍ばねばならないあなた方の運命に対し、私は何を言うべきかを知らない。~『朝鮮の友に贈る書』柳宗悦1920年
韓国映画やドラマを見て気が付くのは、時々セリフにハッとさせられるような詩的表現が多いこと。少女の交流を描いた『わたしたち』ユン・ガウン監督や、『それから』ホン・サンス監督、『ペパーミント・キャンディ』イ・チャンドン監督などを観ると、こういう繊細な、人情の機微や人の痛みを表現できる韓国っていったいどういう国なんだろう?と思う。晩年、詩人の茨木のりこさんが朝鮮詩を原語で読みたくて、韓国語を勉強し始めた気持ちもわかるような気がする
朝鮮の陶磁器や仏教美術を通して、朝鮮半島の人々の繊細さと芸術性のレベルの高さに魅入られたのが柳宗悦。エッセイ『朝鮮の友に贈る書』が書かれたのはちょうど朝鮮半島の3・1独立運動を日本総督府が弾圧したころのことで、関東大震災が起こり朝鮮人虐殺があったのがその三年後になる。日本人の朝鮮人に対するむごい扱いと差別を人づてに聞き、いたたまれない思いで書いたのだろう。この美しいエッセイは、目の前に置かれた李朝の器を通して朝鮮の人々に語りかける、柳宗悦の熱烈なラブ・レターである。
支那もすぐに降伏すべしと思ひ足らんが、案外長く抵抗する―朝鮮も後には追々苦情を申し立て我に背くあらん。自分ばかり正しい、強いと言ふのは日本のみだ。世界はさう言わぬ。 ~『氷川清話』勝海舟
この頃、人が世に処し事に従う様子を見ると、その目的とするところは自己の利益を得るためかそうでなければ名誉権威を求めることであって、精神誠意国を想い、道を行うものは甚だ稀である。 ~嘉納治五郎
柳宗悦は1889年、東京・麻布で藩士の家に生まれた。叔父が嘉納治五郎、母方の父が勝海舟と懇意な関係にあり、のちのバーナード・リーチ、河井寛次郎等との交友関係も含み、宗悦の植民地主義に抵抗する思いや今でいう人権意識の高さは彼を取り巻く人間関係の影響が大きかった。勝海舟は日清戦争にも強固に反対し、日米修好通商条約が不平等なまま、朝鮮半島を植民地化して不平等を押し付けることにも反対し、好戦的な薩長を頂点とする新政府とは対立していた。(今の自民党の欧米には弱腰、その逆にアジア諸国を見下すといった構図はこのころからあったのか・・・)勝海舟は、欧米列強の植民地化に対抗するには、中国、朝鮮半島、日本とアジアの国でお互いに共存、連帯するしかないと考えていたのである。勝海舟の構想していた「儒教文化圏構想」。それは、その後の仏教がベースになっている西田幾多郎の大東亜共栄圏構想とも、国家神道がベースの八紘一宇とも違う。植民地化した朝鮮半島に神社を建立し、日本語教育を押し付けることになったのは、道義的世界統一の理念を示したのは神武天皇という、田中智学の八紘一宇思想によるもの。勝海舟は、儒学者である横井小楠から影響を受けていたため、そうした誇大妄想的な国粋主義や差別による排他主義とは無縁だった。
昔、朱子学と陽明学の本を集中して読んだことがあって、「用」とか「体」とか禅で使われる言葉が頻繁に出てきた事を覚えている。陽明学のほうが「頓悟」(一気に悟る)で、朱子学が「漸梧」(次第に悟る)に似ていたと把握している。禅は陽明学と似ているが、横井小楠が重要視したのは、陽明学の主観主義ではなく、朱子学の「格物致知」であり、合理性と客観性だった。中国の易姓革命(能力主義)は日本では無視され、世襲制になったが、横井小楠は、日本の血縁世襲制度を批判し、能力主義を奨励した。易姓革命の理論では幕府のみならず万系一世も否定されてしまうが、横井小楠は日本人には珍しい純粋な思想家であり妥協がなかったためか、暗殺された。(日本人は、状況に応じて適当に周囲に自分の意見を合わせるご都合主義者が多く、特にそうした修正主義の長州人には小楠のことは到底理解できないだろう、と勝海舟は述べた)また、横井は日本の政治の本質は「鎖国主義」とも、批判している。彼は西洋のキリスト教に対抗できるのは、儒学しかないと考えていたのである。横井小楠は利他を説くキリスト教をとても評価していた。
~参照『横井小楠』松浦玲著
横井小楠の日本批判はとても鋭く、今の日本にもそっくりそのまま当てはまる。「血縁世襲制度」「鎖国政治」と言えば、世襲議員が多く、派閥のことばかり考え、自己保身のことしか頭になく、大衆受けのパフォーマンスしか考えない与党を連想させるし、興味の対象が内向きで視野が狭く、うちわの人間関係や物事に拘泥しがちの日本人の欠点もよくとらえている。利益第一の欧米のやり方は「仁」ではないと批判し、また、ヨーロッパの植民地政策も「仁」の観点から批判し、さらに「開国」を主張した横井小楠。彼は徹底的に朱子学を学ぶことによって道義とともに近代的合理性をも身につけていた。勝海舟は、頭の切れる横井小楠を「天下第一流」と絶賛した。
『幕末の水戸藩』山川菊栄著によると幕末のころには、無学で乱暴な武士、屋敷に押し入り主人を切り殺して書庫の本に火をつける荒くれもの、農家にお金を無心に行く武士、また武士でありながら占い師を信用するなど、堕落した武士やならず者の多い物騒な時代だった。世の中が混乱し、今の言葉でいうと「反知性主義」と暴力が蔓延していたのだろう。
横井小楠から影響を受けた勝海舟や嘉納治五郎も極めて近代的、合理的な判断力を持っていた。勝海舟は蘭学を学び咸臨丸でアメリカに渡っているし、フェノロサに教わった嘉納治五郎はヨーロッパに遊学している、二人とも儒教の合理精神をベースにした欧米文化に対する理解力を持っていたため、土着的な血縁主義や排他主義にはならなかった。嘉納治五郎も平等思想の持主で、学習院院長に任命された三浦梧楼(長州藩)の国粋主義や階級意識の強さとは反りが合わず、三浦による朝鮮の閔妃暗殺事件をきっかけに学習院を辞職、外遊に出る。~参照『柳宗悦と朝鮮』韓永大
・・今の外交家のする仕事は、俺の目には小人島の豆人間が仕事をするように見えるのだよ。
~『氷川清話』
新政府の外交が目先の事しか見えてない、と批判する勝海舟だが、西郷隆盛の人物はとても高く評価している。朝鮮征伐ではなく、礼節正しい外交をと主張した西郷は、大久保らと対立し辞職した(これが西南戦争につながる)当時からアジアに対する「弱腰外交」を嫌う、故・石原慎太郎のような好戦的、タカ派の日本人が多かったのだろうか。道義を重んじた横井小楠。新政府に対して批判的だった嘉納治五郎と、勝海舟。彼らの「仁」を大切にする考え方は、今の、法を無視した何でもありの時代に生きていると、逆にとても新鮮に見えてくる。
・・こうして書いてみると、日本人の本質は幕末のころから大して変わっていないんじゃないかという気もするが、裏金問題を起こしても平気で開き直る、すれっからしの今の自民党議員と比べるのは、さすがに維新政府の人々に対して失礼というものだろう。
そうした二人の影響を受けた柳宗悦。柳宗悦の自宅は朝鮮人の出入りが激しかったので、周りには常に特高の監視があったが、少しもひるまずに宗悦は朝鮮を擁護し、日本政府による同化政策や日本人による人種差別に徹底的に抵抗した。
‥ある国のものが、他国を理解しようとする最も深い道は、科学や政治上の知識ではなく、宗教や芸術の内面の理解だと思う。~『朝鮮とその芸術』
相手の国の文化や芸術を尊重できない人間は、自国の文化・芸術の良さも結局わからないだろう。柳宗悦が朝鮮李朝の磁器を通して知ったのは朝鮮の人々の温かさと寂しさであった。知性というのは、そうした柔らかな感性をベースにして生まれるものだと思う。
幕末、明治、大正時代と違い、私たちはいくらでも情報を入手できる時代に生きている。恵まれた状況にありながら、SNSの悪意あるデマや噂に安易に飛びつくのではなく、つまり、勝手に決めつけたりせずに、まず、白紙になって相手のことを理解しようとするのがフロイトのいう「知性」なのではないかと考える。
※最近、You tuberとして人気ある、30歳になったばかりの若いバックパッカー、バッパー翔太君のファンでよく見る。バックパッカー特有のブロークンな英語でいろんな国のいろいろな人にインタビューしてゆくのだが、その質問の仕方や対応が、どんな人に対する時も彼のリスペクトが感じられて、感じがいい。天然の天真爛漫さで、ロスのギャングだろうがホームレスだろうが、メキシコ国境やインド、インドネシアの未開民族、どんな場所に行っても、相手の懐になんの抵抗なく飛び込んでいく。しかも、番組最後に語る彼の感想が、毎回なかなか深い。インドネシアに世界中のゴミが押し付けられていることも、アメリカのラストベルト地帯に住む人々のことも、ゴミの問題から貧困と格差の問題まで彼のレポートで知った。元々の素質もあるが、おそらく彼の「知性」をはぐくんだのは学校ではなく、彼が今まで出会った世界中の多くの人々なのだろう。こういう生きた知性を持つ若者にどんどん出てきてほしいと、もう二度とバックパッカーというハードな旅ができなくなった年寄りは思う。バックパッカーにはリスクは伴うが、その代わり安宿でいろんな国の大学生と話しをしたり、現地の人と話す機会が多いので、若かったら手軽なパックツアーに参加するのではなく、バックパッカーになってほしい。
若い時の、いろんな人とのいろんな出会いはその人の「知性」となり、また一生の宝物になるだろう。
住宅団地 記憶と再生 №31 [雑木林の四季]
ベルリン・ヘラースト地区の団地
国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治
全棟にエレベーター付設、バルコニーの拡張
通路側から見える部分では、玄関回り、バルコニーの改修、エレベーターの付設などが、わたしの関心の的だった。それらはいずれも改修を際立たせるかのように非常にカラフルに彩色されていて、微笑ましくなった。,
あとで気がついたのだが、わたしはベルリンの団地で片廊下式住棟をみた記憶がない。すべて階段室型である。旧東ベルリンのどこの団地でも中層住宅のエレベーター付設工事がすすめられている。終わっているといえようか。
エレベ一タ-はごく簡易な造りで、住棟に接合している。車椅子ともう一人がようやく乗れる程度の狭い機種だが、高齢者や障かい者対策ならあれで十分で、各階のフロアーに止まる,。それにくらべ、わが公団住宅がごく一部の既存住棟に追築しているエレベーターは建屋と住棟を廊下でつなぐ方式をとり、もっと「立派」だが、階段室の踊り場止まりで、入口トアまではまた階段の上下が必要であり、だからだろうが隔階止まりにしている。金をかけるわりに不便である。エレベーター付設は本体とは独立の設備とみなし、接合型の造りは建築法税上認められないのだそうである。
エレベーターの新設にあわせて玄関回わりを改修し、デザイン、色彩によって玄関ごとの個性化が見られる。
バルコニーを拡張し、ロッジア風に改造して生活空間としての利用価値を高める工夫をしている。それぞれに花を飾り、道ゆく人たちの目を楽しませてくれる。よく確かめなかったが今になって、あれはバルコニーをロッジア風化して一部屋増築にしたほか、バルコニーのなかった側の外壁をぶち抜いてばるこにーを設置したのでないかと、自分の撮った写真を昆ながらそんな気がしてきた。バルコニーの改造等は、エレベーターの付設は別として、どの住棟でも行われているわけではない。全体から見ればまだ一部である、住民合意の形成、工事予算の都合等でおそらく10年、20年と時間をかけての長期計画だろうし、改修の方式、デザイン等も変わっていくのだろう。
外から見ただけでもかなり大胆な改修をしているのだから、内部の階段室や室内の改造にはさらに興味深い。
大胆な団地改造といえば、その手法に減築、さらには住戸の撤去もあるのだろうが、わたしが歩いたこの地区には高層の滅築も長い住棟の分断も気づかなかった。空き家は目についた。空き家の窓には、直径40センチはどのオレンジ色の丸い紙に「ミ一テ・ミヒ(私を借りて)と連絡先の電話番号を書いた貼り紙がしてあるからわかる。わたしの住む団地には階段によっては10戸に4戸、5戸の空き家があるから、窓にこんな貼り紙をしたら、どんな見世物になるか、異常な眺めであろう。
2019年9月に再訪したさい、ミーテ・ミヒの貼り紙は見あたらなかったし、この地区では新築工事さえ見かけた。古い住棟を除却した跡なのか空地だったのかは分からない。地下車庫つきの家族壇住宅149戸の建設と標示している。へラースドルフを歩いてわたしが気づいた団地の現状である。
『住宅団地 記憶と再生』 東信堂
『住宅団地 記憶と再生』 東信堂
地球千鳥足Ⅱ №43 [雑木林の四季]
マツタケ狩り奥義
小川地球村塾村長 小川律昭
小川地球村塾村長 小川律昭
毎年八月末にはコロラドにマックケ狩りに行きたくなる。趣味といってしまえはそれまでだが行きつけになって六年に及ぶ。
降雨量の影響で全然採れない年もある。今までのところ確率は五十%である。にもかかわらず、その時期が来ると行きたい衝動に駆られるのは何故だろう。青年時代、田舎で秋になるとキノコ狩りに行っていた。種々のキノコを採ったがマツタケは一回だけだった、あの見つけた時の快感が今でも脳裡に残っていて、郷愁も含めて忘れられないからだと思う。探ったものを食べることにはそれほど興味はない.
降雨量の影響で全然採れない年もある。今までのところ確率は五十%である。にもかかわらず、その時期が来ると行きたい衝動に駆られるのは何故だろう。青年時代、田舎で秋になるとキノコ狩りに行っていた。種々のキノコを採ったがマツタケは一回だけだった、あの見つけた時の快感が今でも脳裡に残っていて、郷愁も含めて忘れられないからだと思う。探ったものを食べることにはそれほど興味はない.
この地のマックケ狩りの出は、海技二〇〇〇メートルぐらいの唐松林の中である。実際、一人で山に入って探し出すのだが、湿地で別のキノコが生えているような場所にマツタケも生えるのだ。もちろん、コロラド駐在のマックケ狩り大先輩から教わったから言えることだ。時期は八月終わりから。暑かった夏の気温が下がって摂氏一九度ぐらいになってから生え出す。
山に入れば二時間をめどに探すのだが、ただ下を見て歩いているだけではそう簡単に見つけることは出来ない。まずありそうな場所の選定から始める。直径二五センチぐらいの松ノ木の周辺一・八メートル以内の乾燥した場所か、小さな尾根を形成しているところを地面をなめるようにじっくり探すのだ。日当たり確率四〇%の場所がいい。一本見つかればその周辺四メートルに渡ってリング状に点在して生えている。木の根元にもたまにはある。後はしゃがみ込んで根気よく見つけ山すことである。初めの一本を見つけるのがポイント、それは地面の松葉がこころもち膨れ上がっているところ、その松葉の下をかき分けると鎮座まします。大きく膨れ上がったところは別のキノコだ。よくよく見れば松葉がなくても地面が割れている箇所にもある。地面三~六センチと結構深いところにあるから、キノコの周辺を掘らないとうまく採れない。
山は下から登って行く方が見つけ易い。下からだと透かすように見上げられるから膨らみもわかり易いし、大きなマックケなら傘の裏が見える。だが大抵虫が入っており、茎も柔らかくて駄目だ。だがその周辺をなめるように探すことに意義がある。一本あればそれが呼び水と思えばよい。必ず沢山あるはず。誰も採っていないところなら一箇所で十~十五本はかたい。
次のポイントは鹿の糞がかたまってあるところ。松ノ木周辺に彼らが掘った後の穴があいている。ヤツらは匂いで嗅ぎ分けているから間違いはない。その困りを探すことである。最後に人が円周状に採取した後に、遅れて生えたものを前述の要領で狙う。この場合多くは望めぬが二、三本なら探れる。結論として松ノ木の下、この辺で一休みしたいようなところ、キレイで木陰から日もさし、小尾根のある乾燥した斜面に生える確率が大きい。
山に入れば二時間をめどに探すのだが、ただ下を見て歩いているだけではそう簡単に見つけることは出来ない。まずありそうな場所の選定から始める。直径二五センチぐらいの松ノ木の周辺一・八メートル以内の乾燥した場所か、小さな尾根を形成しているところを地面をなめるようにじっくり探すのだ。日当たり確率四〇%の場所がいい。一本見つかればその周辺四メートルに渡ってリング状に点在して生えている。木の根元にもたまにはある。後はしゃがみ込んで根気よく見つけ山すことである。初めの一本を見つけるのがポイント、それは地面の松葉がこころもち膨れ上がっているところ、その松葉の下をかき分けると鎮座まします。大きく膨れ上がったところは別のキノコだ。よくよく見れば松葉がなくても地面が割れている箇所にもある。地面三~六センチと結構深いところにあるから、キノコの周辺を掘らないとうまく採れない。
山は下から登って行く方が見つけ易い。下からだと透かすように見上げられるから膨らみもわかり易いし、大きなマックケなら傘の裏が見える。だが大抵虫が入っており、茎も柔らかくて駄目だ。だがその周辺をなめるように探すことに意義がある。一本あればそれが呼び水と思えばよい。必ず沢山あるはず。誰も採っていないところなら一箇所で十~十五本はかたい。
次のポイントは鹿の糞がかたまってあるところ。松ノ木周辺に彼らが掘った後の穴があいている。ヤツらは匂いで嗅ぎ分けているから間違いはない。その困りを探すことである。最後に人が円周状に採取した後に、遅れて生えたものを前述の要領で狙う。この場合多くは望めぬが二、三本なら探れる。結論として松ノ木の下、この辺で一休みしたいようなところ、キレイで木陰から日もさし、小尾根のある乾燥した斜面に生える確率が大きい。
いずれにせよマックケ狩りは山をドンドン歩くのではなく、地面を透かし、なめるようにゆっくり歩いて、落ち葉上の膨らみを見つけ出すことである。男性より女性の方がゆっくり歩くし集中力があるから向いているかもしれない。ここにはマツダケが必ず生えているのだ、という信念を持つことが大切である。
(二〇〇一年九月)
『万年青年のための予防医学》 文芸社
(二〇〇一年九月)
『万年青年のための予防医学》 文芸社
山猫軒ものがたり №35 [雑木林の四季]
炎 1
南 千代
南 千代
能ヶ谷川での釣りが解禁になった。川は三年おきに禁漁と解禁をくりかえす。これまで、川をのぞき込んでは魚が泳ぐのを「早く大きくなあれ」と眺めているしかなかったのだが、いよいよ釣ることができるのだ。
といっても、釣りは子どもの頃以来である。敵は渓流の女王であるヤマメ。さっそく、釣りの名人である時次郎さんに教えを請いに行った。時さんは、この川の管理を任されており、禁漁中に釣りをしている人を見かけると、葵の御紋のごとく漁業組合の監視員証を見せるのが自慢である。
明日から解禁というその日、時さんの顔はイキイキと輝いていた。懇切ていねいに釣り万を教えてくれ、おまけに釣竿ひとそろいを貸してくれた。翌朝、夜が明けるのを持って川へ降りた。いた、いた。ヤマメが泳いでいる。泳いでいる口元に釣糸を垂れるのだから、釣れないわけがない。またたく間に五匹釣れた。まだ小さな一匹は、キャッチアンドリリース。
必要以上に釣ることはない。すぐに家に引きしけて竹串に刺し、囲炉裏で焼く。まず一匹を山猫軒の主である黒猫のウラに献上し、残り三匹を私たち二人と絵筆で食べる。うまい。身は引き締まっていて、透き通るように白い。
この日の朝は和食。玄米ご飯にフキノトウの味噌汁。まだほんのり温かい産みたて玉子に。たくあえ、梅干し、材料から梅干しにいたるまで、すべて自家製のいつものメニューに、久々の新鮮な魚がついた豪華版である。
この春からは、田の近くに新しく二反の畑も始めることになっていた。地元の人たちと親しくなると、畑地の話は向こうからいくらでもやってきた。
高齢者の多いこの集落では、耕していない田畑が多い。耕してはいなくても、周り近所の迷惑を考えると草刈りなどの管埋はきちんとしておかなくてはならない。作物を作るための草刈りならまだしも、ただ放置しておくだけの土地の手入れは、精神的にもかなり辛い。
きちんと作物を作り、管理し、周りの百姓たちともトうブルを起こさずうまくやってくれる人なら、ただでも貸したいと思っている土地の人は少なくない。が、いったん貸して返してほしくなったときなどに、面倒がおきるような人だと困る。だから、どこの誰ともどんな人ともわからない最初からは、ふたつ返事では貸さない。もっともだと思う。家の場合と同じだ。
そういう点では、私たちは紹介者もいて、ほんとに恵まれていた。「三キロの近くに借りられることになった佃は、元は田んぼだったリ、土砂を埋め立てた地であったりと、それなりに開墾や石除け等を行い、畑にするまでのきつい作業はあったにせよ、向うから「使ってくんねえか」と言われるのは、ありがだいことであった。
冬の間に、借りることになった畑の開墾はすませておいた。玉川村をはしめ、あちこちに少しずつ間借りしていた小さな畑は返した。今年からは、まとまった畑で存分に野菜を作ることができるのだ。
ギヤラリイの方では、ひさ子さんの作品展を開催している間に、次々に新しい企画が生まれてきた。この町の出身だというので訪ねてきてくれたのは、バロックリュートなどの古楽器奏者である立川さん。夫の古くからの友人であるジャズベーシストの井野さんもやってきた。
すると、山猫ギャラリィは今度は猫の目のように早変わりして、コンサート会場に。数十個の椅子は、太い丸太を総動員。時には囲炉裏端お座敷ジャズのスタイルで。古い家は、建具を外せば大広間になり、七、八十人と予想外の人数を受け入れてくれる。
鶏のコケコッコーやヤギのメエメ工、犬のワンワン、蝉しぐれ、とアドリブ参加もあり人も楽器も動物も風も、今、ここにあるすべての状況と生をひっくるめての、山猫ライブである。
やろうとしさえすれば、ほんとになんでもやれるものだ。生越町に住む若手作家たちで、
合同展をやろうという話も持ち上がった。地元作家の作品を、地元の人々にも観てほしい。第一回目の参加作家は十一人。絵画、彫刻、染色織物、陶芸、草工芸、写真、金属、木工などジャンルもさまざまだ。
「この町にも、こんなにいろんな作家がいるんですね。自分の町を何だか見直しちゃった」
町の駅東に住む中川さんが言った。.読女は、牛乳パックの回収などリサィクル活動をこの町で地道に着実に続けている人で、借りているこの家の遠戚にあたる人でもある。うれしかった。
『山猫軒ものがたり』 春秋社
『山猫軒ものがたり』 春秋社
BS-TBS番組情報 №300 [雑木林の四季]
BS-TBS 2024年3月前半のおすすめ番組
BS-TBSマーケティングPR部
BS-TBSマーケティングPR部
第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント


3月1日(金)午後6:30~7:30
3月2日(土)午後7:00~8:00
3月3日(日)午後5:30~6:54
3月2日(土)午後7:00~8:00
3月3日(日)午後5:30~6:54
☆日本女子プロゴルフツアー開幕戦!女子プロゴルフ界を代表する強さと美しさを兼ね備えたトッププレーヤーたちがビッグタイトル獲得に挑む!
日本の女子プロゴルフトーナメントは、南国・沖縄で開幕戦を迎える。
「第37回 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」。
世界基準の4日間競技で開催され、賞金総額も1億2千万円(優勝賞金2,160万円)とツアー初戦から真の強さが試される。戦いの舞台は沖縄県南城市にある美しく戦略性に富んだ琉球ゴルフ倶楽部。華やかな舞台で日本女子プロゴルフ界を代表する強さと美しさを兼ね備えたトッププレーヤーたちがビッグタイトル獲得に挑む。
いぬじかん


3月12日(火)よる11時~11時54分
☆犬好きMC関根⿇⾥&岡部⼤(ハナコ)が送る犬が主役のワンワンバラエティー! 犬にまつわる役立つ情報から感動のストーリーまで、一時間まるごとワンコだけでお送りする超癒し系番組です!
#11 今回は犬とのよりよい暮らしが見つかる大型複合施設のWANCOTTを紹介。
MC:関根麻里 岡部大(ハナコ)
ヒロシのぼっちキャンプ Season8


3月13日(水)よる10時~10時54分
☆ヒロシが自分のためだけにするひとりぼっちのキャンプ。ほんとうの自由がここにある。
#83「バラとヒロシと春雨の森」/#84「大きな岩と俺のお花見キャンプ」(再放送)
4月上旬、雨が降る静岡県富士宮市にやってきたヒロシは、清流沿いのキャンプ場の森の奥でひっそりと佇む苔むした巨石と出会う。巨石のそばを居場所に決めてテントを設営するとさっそく焚き火を始めようとするのだが、すっかり雨に濡れた森の薪にはなかなか火を着けることができない。
今回の主役にとスーパーで買ったうなぎを美味しく焼き上げるには、じっくり熱を伝えてくれる絶品の熾火を作らなければならないのだが・・・。春雨の森で自分なりのお花見キャンプを楽しもうとするヒロシの一日を描く。
海の見る夢 №72 [雑木林の四季]
海の見る夢
―Sky Lark-
澁澤京子
いまだ停戦せず、ますます虐殺非道の続くパレスチナ。正義なんてないんだ、と思いながらCDを整理していたら、『真夜中のサヴァナ』クリント・イーストウッド監督の映画のサントラ盤が出てきた。クリント・イーストウッドのものにしては、異様な雰囲気の映画だったけど、さすがクリント・イーストウッド、映画で使われるジャズ音楽が私の好みだったので以前CDを買ったのだ。特に、「スカイラーク」ってこんなにいい歌だったのか、と感心したのがK.D.ラングというジャズシンガーで、ジャケットには、両手に皿を持って首を傾げた女の子の銅像の写真。あの映画に出てきた、公園の女の子の銅像は「正義」のシンボルだったんだ、と今更ながら気が付く。そこでもう一度映画を見直す事に。サヴァナで起こった事件をもとに書かれた小説が映画化されたもので、「ムーン・リバー」「スカイラーク」「酒と薔薇の日々」「フールズ・ラッシュイン」など数々のジャズの名曲の作詞家であるジョニ―・マーサーの生家で実際に起こった殺人事件。ジョニ―・マーサーのジャズ詩は何となくデカダンなものが多く、ジャズをこよなく愛するクリント・イーストウッドがこの小説を映画化したのも頷ける。
「・・悲惨な話を隠すのがサヴァナ流だ。」~『真夜中のサヴァナ』映画より
ジャーナリストのジョン(ジョン・キューザック)が、サヴァナの名士ジム(ケヴィン・スペイシー)にインタビューするために街に着くところから話は始まる。サヴァナというアメリカに実在するこの港町が実に美しい。街路樹は生い茂り人々に木陰を提供し、歴史ある美しい建物と公園、明るい陽射し、抜けるような青空・・しょっちゅうどこかの家ではパーティが催され、住人は中流階級の裕福な人々が多く、まるで、もてなし上手の老練なマダムのような街なのである。かつてのジョニ―・マーサーの邸宅は、今は骨董商で名を成したジムがそれを買い取って住んでいる。
ところが、ジムのパーティの最中に殺人事件が起こる。ジムと痴話喧嘩になった自動車整備士で男娼でもあるビリー(ジュード・ロウ)が激昂して暴れ、撃ち殺されてしまう。後半は法廷ものになり、犯人とされたジムは優秀な弁護士を雇って無罪になるが・・この映画は、最初に犯人がわかってしまうので謎解きでもない、むしろ映画全体から浮かび上がってくるのはそうした事件の究明よりも、不自然な街の人々の姿。パーティの最中に殺人が起こっても、見て見ぬふりで無関心のまま談笑し続ける人々・・死んだ犬の散歩をする紳士、いつもペットのアブを顔の回りに飛び回らせている男、醜聞をひそひそ囁きあう奥さんたち・・つまり、社交的だが他人に無関心、奇妙な街の人々の姿が浮き彫りにされる。そのため、この街の青空が抜けるように透明であるほど、逆にその明るさが不気味に見えてくる。そして、殺された貧しい青年ビリーの死を悲しむのは、街の人々から密に侮蔑されている男娼仲間のレディ・シャブリだけ。この街の裕福な人々は、男女を問わずビリーと肉体関係を持った人が多いのに,ビリーのような貧しい若者の存在は、社交生活では空気のように無視される。
クリント・イーストウッドが描きたかったのは、起こった犯罪よりも、むしろこの街の人々の異様さだったんじゃないかと思うと、両手に皿(天秤)を持った、銅像の女の子が暗い表情なのも腑に落ちる。社交では何事でも他人事のように語られ、無関心が蔓延、ジムのような権力者がその財力によって罪に問われないのは日常茶飯事のこと。そうすると人々は、理不尽を理不尽とも思わないほど感覚がマヒしてしまうのかもしれない。
「死者と語らないと、生者のことはわからない。」
良心の呵責に苦しむジムの唯一の相談相手、ヴ―ドゥ呪術師のミネルバの言葉。タイトルの『真夜中~』は、ミネルバの呪術が真夜中に行われる事からくる。死者との語りは、内省であり、祈りでもあり、また、音楽の根源もそこにあるんじゃないかと思う。世の中には、他人の苦しみのわかる人と、わからない人がいるだけなのかもしれない。法廷で無罪判決が出てから、ジムは心臓発作を起こして死ぬが、最期の瞬間にジムが見たのは、殺されたビリーの微笑む姿で、それはビリーがようやく復讐を遂げた微笑みなのか、それともジムへの愛なのかは神のみぞ知る、だろう。
一見、人種差別もなく平和、多様性に寛大でリベラル、経済的にも豊で美しい街サヴァナ。しかしその裏には経済格差と貧困、人種差別、ゲイ差別というものが密に隠されていて、原作のタイトルは『Midnight Garden of Good and Evil』。クリント・イーストウッドは、原作にはなかった、両手に皿を持つ女の子の銅像(正義の象徴)を登場させた。正義というものが不均衡なものでしかない今の世界で、この銅像の少女の暗い表情は妙に脳裏に焼き付く。もしかしたら、正義は死者との語りの中に存在するものなのかもしれない。
※ここまで書いていたら今、(2月26日夕)、アーロン・ブシュネルさん(25)米兵が、ワシントンのイスラエル大使館前で抗議、パレスチナ解放を叫びながら、焼身自殺するという痛ましいニュースが飛び込んできた。今、パレスチナで連日起こっている虐殺が、感受性の強い一人の優しいアメリカの青年の心を踏みにじったのだ。さっそく、ブシュネルさんに対し「精神疾患」というレッテル貼りする人々が出てきたが、もしそうであるならば、おそらく世界は、彼よりもずっと狂っているのに違いない。
アーロン・ブシュネルさんの魂が安らかでありますように。
住宅団地 記憶と再生 №30 [雑木林の四季]
18.ベルリン・ヘラースドルフ地区の団地 Berlin-Hellersdorf
国立市富士見台団地自治会長 多和田栄治
●ヴーレタルWuhletal駅から
メルキッシェス・フイアテルが旧西ベルリンの大団地の代表とすれば、旧東の代表には「へラースドルフ団地」があげられる。
2010年の10月15日、団地再生の好例として紹介されている団地をこの目で見たくて、へラースドルフ駅にむかうU5バーンに乗った。外を眺めているともう何駅も手前から緑のなかに高層の住棟が連続して見えはじめたので、あわててヴーレクル駅で下車した。へラースドルフ駅の4駅も手前である。団地の所在を予めよく確かめずに来てしまったのが失敗だった。進行方向にむかって駅の左前方、歩いて数分のところに団地がひろがっていた。団地のなかで「ここはへラースドルフか」と聞くと「そうだ」という。団地の名称を聞いても、けげんな顔をして答えてくれない。行政区はたしかにへラースドルフだが、これが団地名ではなさそうだし、固有の団地名が必ずあるとは限らない、と思えてきた。団地内のすべての通路には通り名があり、玄関ごとに番号があるのだから、それだけで住所表記は十分である。団地名はないのかもしれない。団地の入口近くに「住宅建設組合ヴーレタル」WG Whletal e.Vの建物があった。
あとで調べたら、この組合は旧東ドイツのベルリン、ケムニッツ、ノイブランデンブルク、シュヴェーリンの建設企業の連合体であり、1980年代に3,000戸余りの住宅をへラースドルフ地区に建設し、企業本社の所在地名を建設した居住地区の名にしている。わたしが歩いたのは、ルートヴィヒスルスター通りとパルヒマ一通りがかこむ「シュヴェーリン住区」であった。近くのヴーレ川沿いは緑の回廊になっている。
外壁は白色か薄茶色を基調にした、まだ新しく見える、すてきな団地である。駅に近い住棟は5階建て、奥にむかって高層化、といっても6~7階建てである。ベルリンでは団地の計画的なリノベーションが90年代にはじまっている。ここでも玄関口やバルコニーの改修と塗りかえ、エレベーターの追築などの工事が施されている。その後さらに改修、近代化が進められている。
団地内を歩いていて、どの住棟も長大であることが気になった。その後グーグルマップでみると、内側の何棟かが工事中のようだったし、いまその区画=公園になっている。撤去されたのであろう。
寮内については知る由もないが、外観上の改修工事を一部この団地でも見ることができた。団地の中央に4階建ての住宅管理事務所があり、管理窓口で喫茶店も経営し、かなり大きな建物のなかは会議室やクラブ活動のための部屋などになっている。
ここにいても「へラースドルフ団地」行きに気がはやり、早々とこの団地に別れをつげ、へラースドルフ駅にむかった。ただし、ここでは地理的にヴーレタルに接したカオルスドルフ・ノルトへの訪問記を先にしるす。
●カオルスドルフ・ノルトKaulsdorf-Nord駅から
カオルスドルフ・ノルトもよく聞く地区だから、2019年にベルリンに来たさい9月7日に訪ねてみた。U5バーンのヴーレクル駅のつぎである。駅の両側に5~12階建ての住棟群がせまっている。
ヴーレタルとカオルスドルフ・ノルトとは、居住地区がつながっていて境界があるわけではなく、歩きはじめた地点はちがうが、9年前と同じところまで足を延ばしていることに気づいた。団地の風景も、思いだせば似ている。そのはずである。この地区とヴーレタルは、旧東ドイツの同じ各都市の建築家たち(おそらく労働者も)が担当し、建物とその配置、空間のデザインに覇をきそったと記されている。住棟ブロックそれぞれに個性的ではあるが、光景は両地区共通の印象をうける。まえに来たときよりも色彩的にいくらか鮮やかに感じるのは、9年のあいだに団地の改修が進んだせいかもしれない。
カオルスドルフ・ノルトは、ツェツイリエン通りをはさんで南北に、第1区と第2区にわかれ、1979年から86年にかけて、3~5室のアパートがそれぞれ5,486戸、2,050戸建設された。1区には、保育園6、幼稚園11、学校6、ショッピング・センター3、レストラン5のほか社会施設があり、2区にも各種施設が設立されている。建設されてベルリン市区に引き渡され、管理(所有)は複数の半ば公的な組織に託されたのであろう。わたしが歩いたのは、ギュルツオヴェル通りとリリー・ブラウン通り界隈であるが、この辺りはシュタット・ウント・ラント(都市と土地)社Stadt und Land Wohnbauten GmbHが管理している。
住棟はどこもほぼ5階から、高くて12階建てで、正方の中庭を大きくコの字型、あるいはL字の組み合わせ型にかこむかたちで建てられている。駅近くは11~12階住棟が建ち並ぶ。ある12階建て高層住棟はl階が住宅ではなく事務所、集会所などに共同使用されている。その先には、5~6階建てがつづく。
5~6階建てには明らかに改修の跡がみられる。エレベーターの付設とバルコニーの拡張である。当初エレベーターはなかったのであろう。いまではすべての住棟の階段ブロックごとに1・5メーター四方の赤褐色のボックスが付設されている。表玄関脇が多いが、裏口側への付設もみかけた。バルコニーの改造はすべての住棟ではなく、おそらく住民合意にたっした階段ブロックごとに施工されているのだろう0バルコニー枠を増築し、張り出させてロッジア風に改造し、居住面積の拡大にもなっている。
『住宅団地 記憶と再生』東信堂
『住宅団地 記憶と再生』東信堂
地球千鳥足Ⅱ №42 [雑木林の四季]
こんなところで日本人5人と会った!
~べリーズ~
小川地球村塾村長 小川律昭
ベリーズは全体的には安全な経済成長過程国で、カリブ海の水はコバルト色だ。だが空港のあるベリーズ・シティは少々治安が悪い。我々は恐れず第一夜をここに取り、着いた早々まず市内を散策した。街角でビニール袋売りの裁断マンゴーを食べている、痩身の若い日本人女性に逢った。テレビ取材の手伝いで半日雇われたという。彼女はTさんといい、「キーカーカー島に住んでいる」と言った。忙しそうだったのでそれで会話は終わり。日本人男性2人がその傍におり、カメラマンと渉外係のようだった。テレビ番組、「世界の村で発見! こんなところに日本人」の取材中とのことだった。この取材陣に「ご夫婦とマイアミからの航空機で一緒でした」と言われたがこちらは記憶になかった。リュックを担いだ合計156歳の夫婦は目立ったのだろう。
ベリーズ・シティは壊れかけた建築物やバラック建ても多く、街並みは汚い。空港も古くて質素、航空機への乗降は徒歩だ。首都のベルモパンには空港がないのでここが国際空港、うらぶれた都市である。200年前宗主国イギリスから運ばれたレンガで建造されたセント・ジョーンズ教会と、カリブ海に面した総督官邸を見学したが、現今は迎賓館、熱帯植物に囲まれた優雅なたたずまいだ。刑務所だった博物館は厳重な鉄格子塀に囲まれていた。政策として強調しているのはカリブ海のレジャー観光とリゾート産業のようだ。
頭髪をアフリカン・アメリカン状に編んだ女性から声がかかった。「日本人ですか?」と。2時間半バスに揺られ、サン・イグナシオに着いたところだった。ワイフと日本語を交わしたのを聞いたのだろう。黒く日焼けした、日本人にしては大柄な女性で、10ドルかけてネイティヴのように髪結いしたという。ここ、サン・イグナシオでは最高のホテル、カル・ペチ・リゾートを選んだ。
ベリーズを代表するシユナントゥニッチ遺跡は密林に覆われた丘の上にある。9世紀頃繁栄した神殿都市という。高さ40メートルのピラミッドは保存状態もよく壁面には神や踊る人、怪物や貝殻なども刻まれており当時の文明を偲ばせる。ホテルから見下ろせるカル・ペチ遺跡は歩いて数分の距離、紀元前3世紀から紀元後8世紀にかけてのものが混在し、独特のマヤ・アーチ状の構造が特徴だ。
南のリゾート地プラセンシアのスーパーで会った日本人女性はワイフが私を「お父さん!」と呼ぶ声を聞き、話しかけて来た。夫はアメリカ人、政府系の仕事をしていて定年後ここに来て家を建築したと言う。日本人が懐かしいのか30分も立ち話をした。物価も安いしカリブ海の温暖気候が気に入ったのだ。この国には16人ほどの日本人が居住するとのことだ。
プラセンシアは昔の漁村、今は高級リゾート地でホテルもレストランも高価だ。その関連で仕事もある。シーズン・オフで人影を見かけない海水浴場だった。砂浜沿いの貸小屋は空家。ホテルのカヌーやサイクリング車で楽しめた。
キーカーカーは俗化していて砂の小島ではなくなった。サン・ペトロも桟橋やマリンレジャーに人が集まり過ぎて海辺を汚している。バリア・リーフやブルー・ホールへ船で出かけて珊瑚礁の海底を覗くほうがいいだろう。
(旅の期間‥2013年 律昭)
珍遇が取り持つ縁は地球の一角から
「事実は小説よりも奇なり」といわれるが、誰しも体験があるだろう。人と人は見えない糸で繋がっていると思わざるをえない事件がままある。人生行路はある時重なり合い、交友範囲が拡大し、生きる楽しみも増える。覚えている範囲の珍遇、奇遇を紹介しよう。
成田からの国際線ダラス行きの機中、飛び立って2時間後、フライトアテンダントが我が隣の空席に客を連れて来てよいか尋ね、了解したら日本人女性が座った。驚いたことに、彼女はシンシナティの我が家のご近所イーナおばさんの所に以前寄宿していた。その後日本で結婚したが、高校、大学時代ともイーナおばさんと暮らしたという。我々夫婦もイーナと付き合っているが、そもそも彼女とのご緑は、別の寄宿人をイーナが空港に迎えに出た折、私が近所と知り同乗させてくれたことが始まりで、今も信頼感で結ばれている。
エストニアのタリンで、隣国ラトビア行きのバスの切符を求めていた時、小柄な女性が列の後ろに。ブラジルから来た日本人夫婦だった。私の元勤務先のブラジル支社駐在員が共通の友だちだった。バスがすぐ出るので名前を交換しただけで別れたが、隣国ラトビアの中心街リーガの街中で「小川さ~ん!」と呼ぶ女性の声。よくも同じ時間に同じ街の一地点をすれ違ったものだ! 5分ずれたら会えてはいなかった(ラトビア共和国の項参照)。この国はホテル探しが大変な国だった。やっと見つけた小ホテルのエレベーターで「やあ、小川さん」と今度は旦那さん。これが何の打ち合わせもなしで3度目の出会いだった。朝食を共にして話をしたら、お互い日本に生活拠点を置き、定年後彼らはサンパウロ、我々夫婦はシンシナティに活動拠点を置く元駐在員だった。似た夫婦同士、バルト三国をうろついていたのだから奇遇だろう。再々会は打ち合わせをして、ブラジルはサンパウロの日本人開拓時代の博物館で。もちろん日本でも国分寺で会食を楽しんだが、世界各地で計5回も会ったのだ。
彼らとの出会いは霊感に導かれた必然的偶然とでも言えるのではなかろうか。海外で日本人らしき人に会えば私はよく話しかける。好奇心が働くからだ。「地球の一角でいつ人との出会いや緑が始まるかわからない」と期待しつつ、行動する我が好奇心とその果実に乾杯! (2015年執筆 律昭)
『地球千鳥足』 幻冬舎
『地球千鳥足』 幻冬舎
山猫軒ものがたり №34 [雑木林の四季]
ムラの名人たち 2
南 千代
私が料理を習っている間、夫は薪集めの毎日だった。ガスのない暮らしが不都合もなく続いていたため、台所に風呂に暖房にと、一年に使う薪の量は、四トン車でおよそ二、三台分。
夫はコーさんに紹介されて、キコリの名人である小沢さんの山仕事の加勢に行くようになっていた。一緒に出かけて仕事の手伝いをし、不要な枝を薪用にもらってきていたためである。
木には「伐り旬」とキコ与たちが呼ぶ伐りどきがある。秋から冬にかけての季節だ。つまり、木が根から水分を吸い上げていない時期である。この頃になると、キコリたちは忙しい。倒された木の、要らない枝を集める夫も忙しい。地下足袋に脚絆(きゃはん)を巻き、弁当とチェンソーとついでにカメラも持って、彼らと共に、朝七時半に家を出る。
枝といっても直径二十センチ、長さ数メートル。とても男一人が持てる重さではなく、チェンソーで切った後、クレーンで積み下ろしする。こうして何日も山に通った後、はじめて薪になる材料が集まる。
ケヤキ、カシ、エノキ、ナラ。集めた木は、切りやすく割りやすい生木のうちに薪にする。ストーブに入る五十センチ程の長さに切り揃えた後、斧で割る。割る作業は、薪作りの過程のフィナーレみたいなものだ。
これを家の周りにグルリと積んで半年ほど乾燥させた後、薪になる。灯油を買ってきて使うことを思うと、おそろしく時間がかかるのは、米や野菜作りと同じである。
「何だって今の世の中は、買った方が安くつくよ。でも……」
と夫は、囲炉裏に薪をくべながら言う。
「薪が暖めてくれるのは、こうして燃えている時だけじゃないんだよ。チェーンソーを振り回している時も、薪割りをしている時も体があったまるよ」
キつりたちとのつきあいやおしゃべりは心を暖めてくれ・家の周りに積まれた薪は、断熱材代わりとなって家自体をも暖めてくれるというわけだ。
さて、キコリたちの主な仕事はもちろん木を倒すことだが、伐り倒す行為自体は、米作りにおける田植えや稲刈り、薪作りにおける薪割りと同様、作業全体のクライマックス的一部にすぎない。チェーンソーが使えさえすれば、木を伐ることは誰にでもでき、名人とはならない。
しかし、たとえば。木のすぐそばに家や電線があったら、大木が杖を張ったその姿のまま倒れる空き地がなかったとしたら、単純に根元を伐るだけで木を倒すわけにはいかない。
地元では空師と呼ばれている名人・小沢さんの仕事は、そのような木を伐ること。作業の大部分は、十数メートルの高木の上で行われる。
はしごも届かない高い木には、クレーンで移動する。クレーンのフックに足を乗せ、サーッと木の頂上あたりに運ばれると、木に飛び移り、まるでセミみたいにピタリと張りつく。そこで足場を確保しながら、チェーンソ1でまず枝の先を切り落とす。
手頃な足場がないときは、ロープで腰を木に縛りつけた格好でチェーンソーを奮う。太い枝は、クレーンのロープで枝を縛った後に切り放し、吊られた状態で下ろす。胴体だけになった木も同様に上から少しずつ、つめていく。
クレーンアームの位置や木の重心を見極めないと、木を吊った位置や切り放した角度によって空中で木が安定を欠いて大きく振れ、危険を招く。
木が倒れても大丈夫を長さにまで切りつめた後、地面に降り、予定した方向と場所へ木を倒す。ようやく、根元へチェーンソーを入れるわけだ。望む方向へ木を倒すには、あらかじめ木の倒す側に、角度をつけて切り込みを入れ、受け口を作る。反対側にチェーンソーを入れると、木は受け口の中心に向かって倒れることになる。
このように、空の上で仕事をする空師は、近隣でも数えるほどしかいないとか。倒せる高さにまで木をつめた後、隣の木でもう一度同じ作業をしなければならない場合がある。そんなとき、地面に降りて再び隣の木に登るのは時間がかかる。どうするかというと、木から木へロープを渡して空中移動、ロープを伝って隣の木まで這っていく。軽業師顔負けの芸当である。
小沢さんが木の上で作業をしている間、一緒に仕事をする他のキコリたちは、ロープを引っ張ったりして彼の作業を助ける。落ちてくる枝を集める、チェーンソーで整理する、運ぶ、トラックに積むなどの作業もある。
倒した後は、木の売れる部分は市場に持って行き、商品価値のない枝などの部分は、処分する。夫は作業やトラックの運転を手伝い、この部分を薪用にもらってくる。
夫は、加勢の合間に小沢さんの仕事ぶりを、写真に撮っていた。しかし、その身のこなし、スリリングな速さや強さに、唖然として見とれてしまい、つい、手の中のカメラを忘れてしまうことも度々あるらしい。キコリの加勢はまだまだ続きそうだ。
チェーンソーを振り回すおかげで、夫の腕にはポパイのようなカコブができた。
「南さんはカメラマンにしとくのは惜しいや、うちで働かねえか」
夫は、小沢さんに誘われ、苦笑していた。
『山猫軒ものがたり』 春秋社
『山猫軒ものがたり』 春秋社


